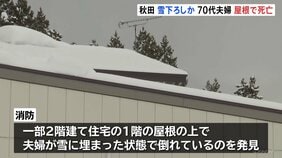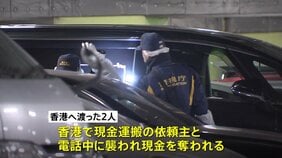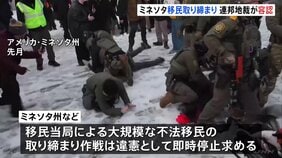◆都合の悪い証拠「探したけど見当たりませんでした」
神戸:どんな証拠があるか、弁護側はわからないですよね?
鴨志田:そうです。だから弁護側は当てずっぽうで「こんな証拠があるんじゃないですか?」みたいなことを言って、検察側が「いやそれはありません」という不毛なやり取りを延々再審請求の手続きの中でやり続けて、それだけで長い時間がかかっています。
鴨志田:袴田事件の場合、第1次再審請求の27年間で証拠は1点も開示されていないんです。「5点の衣類」のカラー写真とネガは、第2次再審になってから裁判所が勧告をして、やっと出てきたものなんです。勧告してくれなかったら、今回のような再審開始の確定まで行き着けなかったかもしれません。どういう証拠があるのかさえわからない状態で、手探りで何十年もかけて証拠開示を求めるなんてことを強いられているのが現状なんです。
神戸:証拠は、検察のものじゃないですよね?
鴨志田:私達の税金を使って彼ら捜査機関は証拠を集めるわけですから「公共財」ですよね。真実を発見するために私達の税金を使って集められた「公共の財産」だと考えるべきだと思うんです。
神戸:当てずっぽうで何か当たった時に出てくる。
鴨志田:検察官は証拠開示勧告に対しよく「不見当」(探したけど見当たりませんでした)と言うのです。袴田事件の場合も、「後で別のところを探したら出てきました」と、幼稚園児の言い訳みたいなことを言うんですね。
神戸:「不見当と言っていても、本当はあったじゃないか」という疑念さえ残ってしまいます。
鴨志田:その通りです。
◆「捜査機関が捏造」ありうるのか
神戸:ある友人が、子供から「証拠の捏造なんて、警察が本当にするのか?」と聞かれた、というんです。「そんなこと信じられない」と。友人は「どう答えていいか困った」と言っていました。「5点の衣類」は捜査機関による捏造だった可能性が高いとまで言われているわけですが、「こんなことが本当に世の中にあるのか?」と子供から聞かれたら、なんと答えたらいいんでしょうか?
鴨志田:それは、率直に「あるのだ」と言わないといけないと思うんですね。再審の手続きが不明なまま、大正時代の刑事訴訟法の規定が、ほぼ1世紀以上手付かずでいる理由は、国民の無関心だと思うんです。なんとなく、「裁判所はちゃんとしてる」「検察や警察はちゃんとやってる」という、漠然とした根拠のない信頼を国民が司法や捜査に寄せているからです。
鴨志田:事件の中で捏造が指摘されたり、実際に判明したりしたのは、別に古い事件だけじゃありません。例えば、村木厚子さんの事件(郵便不正・厚生労働省元局長事件)では、特捜検事がフロッピーディスクを改ざんしていました。ああいうことって、あるんですよ。「ある」とわかった時、国民がもっとちゃんと声を上げて、批判して「変えていかなきゃいけない」となっていかなければ、ずっとこのままのことが続くと思うんです。