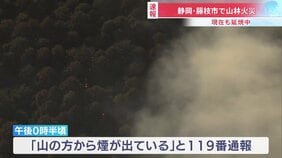「ニュースは歴史のデッサン」
本田圭佑さんのポストで、1次史料が4種類紹介されていました。1次史料とは何か?本人が書いたものを言うわけです。本田さんが挙げていた1次史料には、兵士の日記・書簡をまとめた「本」が上がっていましたが、歴史学で厳密に言うと2次史料になります。元の手紙や日記が1次史料です。
しかし、実物にアクセスできる人は限られています。だから、歴史学者の書いたきちんとした史料集を、学者以外の人が参照して1次史料だというのは許されると思います(歴史学者であれば、本当にこの通りかどうか確かめなければならない必要があれば調べるべきかもしれません)。
ここに出ている史料は、防衛研究所がまとめたものだったり、「『南京事件を調査せよ』に引用された兵士日記」だったり。『「南京事件」を調査せよ』を書いた清水潔さんは、日本テレビ出身の極めて誠実なジャーナリストで、僕もよく知っています。こういう人が引用してきた兵士日記を読んで「1次史料を読んだ」と言ってもいいと思います。
【清水潔著『「南京事件」を調査せよ』(文芸春秋社、2016年、1,650円)】
各方面から大絶賛のテレビ番組『日テレNNNドキュメント 南京事件 兵士たちの遺言』が、大幅な追加取材で待望の書籍化!77年目の「調査報道」」が事実に迫る。「南京事件」は本当にあったのか?なかったのか?戦後70周年企画として、調査報道のプロに下されたミッションは、77年前に起きた「事件」取材だった。「知ろうとしないことは罪」――心の声に導かれ東へ西へと取材に走り回るが、いつしか戦前・戦中の日本と、安保法制に揺れる「現在」がリンクし始める…。伝説の事件記者が挑む新境地。
清水さんの話をしましたが、歴史学の姿勢は実はジャーナリズムとかなり共通しているのです。「この人の証言って本当?」「私にはこう言ったけど、なんか意図を持っていない?」「そういうニュースを流させたいという意図があるとしたら、それはなぜ?」。そういうことを取材で考えるじゃないですか。どこまではファクトで、どこからがその人の意見だなと分別しつつ、私たちもニュースを伝えていきます。
雑誌『サンデー毎日』の元編集長で、僕が尊敬しているジャーナリストの牧太郎さんは、日々の新聞記事のことを「歴史を最初にデッサンする仕事なんだ」とおっしゃっていました。一日一日の新聞記事は、その日で消費されていってしまうけれど、それは歴史のデッサンである。「それはそうだな」と思いました。私たち放送局のニュースも同じです。
でも1日で調べ切れないものが当然あるわけで、1週間でまとめて、1か月、1年でまとめて、10年でまとめて……とブラッシュアップされていくと、だんだん史実に近くなっていく。こういう作業が報道(特に調査報道)だとすると、「歴史学とかなり共通しているな」と思うのです。
自分に都合よく記述しないためのルール
歴史学の「お作法」は、史料批判以外にもあります。一部だけ紹介します。
2つ目のお作法は、「参考文献、引用元をはっきりと示すこと」。どうしてこの結論になったのか、その根拠となる文書は何なのか。これによって、他の人が再調査できる。自然科学で言えば、再実験が可能になるということです。
3つ目は、「先行研究を踏まえること」です。前にこの問題を研究した方が、こういう文書を引用しながらこう記述をしている。これを批判しても全然かまわないのですが、「先行研究の一部を踏まえて、こうです」「いや、この一部は否定したいから、こうです」とか先行研究を必ず踏まえることが、歴史学では必要なのです。事前に研究されているものを尊重しないといけない。
4つ目は、「ミクロとマクロを分けて考えること」なんじゃないかと僕は思っています。建築学に「神はディテールに宿る」という言葉があります。報道の仕事に就いた時に新聞社の先輩から「ディテールにこそ神が宿るからな。しっかり細かいことをしっかり書け」と言われたことがあります。これは非常に重要です。
でも逆に、たった1つの事象に光を当てて、ディテールを自分に都合よく使っちゃうことも可能です。例えば、ある町に裕福な家が1軒ありました。その方にインタビューをして、豊かな生活を聞き取りました。その家があるから「町全体が裕福だ」と言っちゃったら、間違いですよね。ほかの人はそうではない。一部が正しくても、全体像がゆがんでしまったら……。そういうミスリードは、学問でもないし、報道でもないですよね。