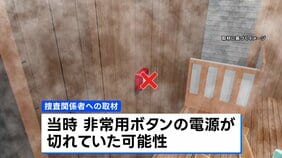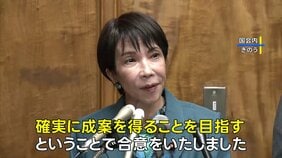(3)シカと稲に共通する「生命のサイクル」
シカは、諏訪信仰の中で非常に重要な役割を果たしています。中世の古文書には「鹿なくてハ御神事ハすべからず」と書かれています。生贄(いけにえ)として、シカやカエルなどの生き物をささげる風習が残っています。弘理子監督は舞台あいさつで「シカの角の成長と、稲の生長のサイクルが合致するからではないか」と話していました。

雄ジカの角は4歳にもなると、秋には枝分かれして1メートル近くになります。角は冬の終わりにポロリと落ち、春になると植物のように再び伸び始めるのです。

弘監督は「初夏に田植えをし、冬に入る前に収穫する稲の生育のサイクルそのものではないだろうか」と指摘します。シカを捧げるのは農耕の豊穣をもたらすことを祈る神事にふさわしいと、古代の人が考えたのではないか。そして、生があり、死があり、食べたら自分の肉になる。また生まれて、命が巡環する。

このサイクルが自動的に動いているとは思わなかった古代の諏訪の人々は「この世界を司っている何かがいる」と考えました。それを「ミシャグジ」と呼んだのではないだろうか、と弘監督は考えています。

考えてみると、アニメ『もののけ姫』に出てくるシシ神は、シカのような姿をしていて、生と死を司ります。森の中で、夜になるとデイダラボッチ(巨人)になり、朝になるとまたシシ神に生まれ変わります。ここも、映画『鹿の国』と似ているなと思いました。
(4)明治以前の豊饒な宗教環境

現代の諏訪大社でも、神事に備える贄(にえ)としてカエルやシカの肉が使われますが、映画の冒頭には動物愛護団体の「諏訪大社よ 動物を殺すな」という大きな横断幕が映ります。それについての論評や団体の主張については映画で触れていませんが、初めにその映像が出てハッとしました。それが頭の中に残っていて、鑑賞者はその後に贄が供えられると「これは許されるのかどうか」などと思いながら観ていくことになるのです。

「動物愛護」という感覚は古代の人にはありませんでした。しかし一方で、生物の存在がなければ自分たちも存在していないということ、それに対する感謝の神事でもあるはずです。現在でもさまざまな批判はありますが、縄文時代から1万年以上、この列島の歴史は続いています。そのころには神社も寺もなく、「日本」という国の名前も、「天皇」という存在もなかったのです。太古の昔から、循環する命への祈りはずっとあったはずです。それがおそらく、諏訪信仰の中には残っているのです。
『鹿の国』というドキュメンタリー映画は、現在の諏訪信仰を丹念に追う中で、当時の人々の「祈り」「憧れ」「畏れ」というような、つまり「撮れないもの」を描こうとしています。これは、なかなかすごいことだと思いました。

僕はちょっと保守的な人間なので、明治の官僚が作った近代天皇制より、古代からのこういったものにすごく魅力を感じます。靖国神社もそうですが、明治以降に制度化されたものを「日本の伝統」と呼ぶのは、どうも腑に落ちません。列島に暮らす者の末裔として、人の祈りや心をすごく意識しています。この『鹿の国』の中にはそういうものが描かれていて、かなりおすすめです。
◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)
1967年生まれ。学生時代は日本史学を専攻(社会思想史、ファシズム史など)。毎日新聞入社直後に雲仙噴火災害に遭遇。東京社会部での勤務後、RKBに転職。やまゆり園事件やヘイトスピーチを題材にしたドキュメンタリー映画『リリアンの揺りかご』(2024年)は各種プラットフォームでレンタル視聴可。ドキュメンタリーの最新作『一緒に住んだら、もう家族~「子どもの村」の一軒家~』(2025年、ラジオ)は、ポッドキャストで無料公開中。