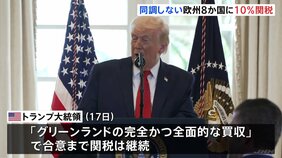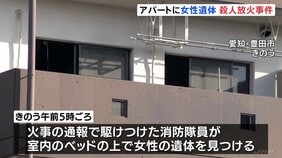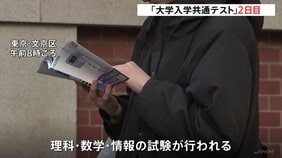「感動ポルノ」として消費される側面も
そして指摘しなければならないのは、オリパラに過剰なストーリーが求められてしまうことです。特に、パラリンピックなど障害者スポーツでいわれるのが「感動ポルノ」という言葉です。身体障害者がスポーツなどに真剣に取り組み奮闘する姿が、健常者に感動をもたらすコンテンツとして消費されていることを指します。
「ポルノ」という言葉は過激ですけれども、これはオリンピックにも当てはまると思います。アスリートがどういう姿勢で、またオリパラをどう位置づけて競技をするかは全く自由なはずですが、これについてはオリパラをことさら強調する一部の報道のあり方にも、問題があると思っています。
ゴルフの全英オープンを前に、「オリンピックを占う大会」とする報道がありましたが、私は強い違和感を覚えます。その競技の最高峰の大会よりオリンピックが上位にあるような見方をするのは自由ですが、私は支持できません。
行きすぎた商業主義からの脱却を
こうしたオリパラ、特にオリンピックが抱える問題の根底には、1984年のロサンゼルス大会を起点とした商業主義の行きすぎがあることは間違いありません。この問題は話し始めると番組5回分くらい必要となりますので詳細には触れませんが、これまでオリンピックを支えてきたマクドナルドやトヨタ自動車といった世界的大企業がスポンサーから手を引く動きを見せていることは、特にオリンピックの影響力が低下している表れとみることができます。
東京大会を振り返れば、さまざまな問題を抱えながらも何とか終了できたのは、アスリートの力があったからにほかなりません。あらゆるイベントをビジネスチャンスと捉えることを私は決して否定しませんが、アスリートファーストといいながら、実際にはビジネスファーストに、もっといえばIOC=国際オリンピック委員会ファーストになっていたことが、東京大会では贈収賄事件や談合事件として顕在化したとみることもできます。
26日からパリ大会が始まります。いろんな種目で世界の一流アスリートのプレーに注目していくことはもちろんですが、今後のオリパラのあり方についても考えながら、そのレガシーを探っていきたいと思います。
◎山本修司(やまもと・しゅうじ)

1962年大分県別府市出身。86年に毎日新聞入社。東京本社社会部長・西部本社編集局長を経て、19年にはオリンピック・パラリンピック室長に就任。22年から西部本社代表、24年から毎日新聞出版・代表取締役社長。