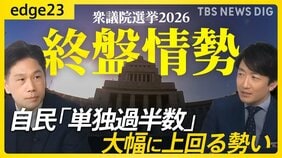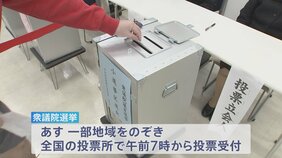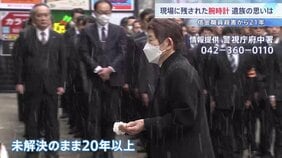43人が犠牲となった雲仙・普賢岳の大火砕流の発生から3日で34年です。災害の記憶の継承が課題となるなか被災当時、小学生だった女性が地元の子どもたちに自身の体験を語り継ぐ活動を行っています。
雲仙岳災害記念館に勤める長門亜矢さん。34年前の6月3日、小学3年生だった長門さんは普賢岳のふもとに位置する島原市安中地区の自宅にいました。

(長門さん)「火砕流が発生した時間は私は家に一人でいたので、テレビを見ていて異常なサイレンの音に気付いて外に飛び出してるんですけど。今日みたいに天気のよくない日だったんですけど、山の方を見たら色がない。何があっているのか分からない怖さ。」
大火砕流の直接の被害は免れたものの自宅周辺が「警戒区域」に指定されたことなどから長門さんは、この日から親戚の家や仮設住宅での生活を余儀なくされます。そして、間もなく長門さんの自宅があった「安中地区」を大規模な土石流が繰り返し襲いました。

(長門さん)「上流のどこどこまで土砂が流れてきてるみたいだよっていう話を近所の方と両親がしてたのは知ってたんですけどまさかこの川から土砂があふれてくるっていうのは想像もできなかった。私の家は原型留めていましたけど、地形によっては被災の仕方も違いましたし、目の前の家はほぼ全壊。天井近くまで埋まっているような状況ですし、家そのものが無くなっているところもたくさんありましたし。」
5年ほど前から、市内の子どもたちに自身の被災体験を話し始めた長門さん。きっかけは、長門さんも母となり2人の子供を育てるようになったことでした。

(長門さん)「自分自身が子供を産んで親になったときに当時の状況を思い出すと自分の子供が重なって見えて、もし自分と同じ状況に置かれていたと考えたらすごく恐怖を感じたんですね。もしもが起こったときにみんなが自分の命を守れるような環境を作っていく。」
「いのりの日」の3日、長門さんは地元の中学校で講演を行いました。話したテーマは「島原で生きるということ」。

(長門さん)「噴火や地震などの自然現象は大切なものをあっさり連れ去り、失われたものは2度と戻ってきません。防災に『十分』や『絶対大丈夫』というのはありません。普段から安否確認の方法や集合場所などを家族としっかり話し合っていてください。」
(男子生徒)「火山がこわいものだなと改めて思いました。」
(女子生徒)「家族にきょうの話をして避難場所の確認をしたいと思いました。」
自分の命は自分自身で守れるようにしてほしい。長門さんは、今後も講演などを通して、次の世代に普賢岳災害の教訓をつないでいきます。