伊方原発3号機について、愛媛県内の住民などが運転差し止めを四国電力に求めていた裁判で、松山地裁は18日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
主な争点は①地震に対する安全性、②火山に対する安全性、③重大事故が発生したときの地域住民の避難計画、この3つです。
【①地震に対する安全性】
地震対策の評価について、原告側は「地震に対する四国電力の評価は過小だ」とした上で、伊方沖の活断層「中央構造線断層帯」についても、より被害が大きくなるとされる南(原発側)に傾いた「逆断層」の可能性も考慮すべき、などと主張していました。
一方、四国電力は「最新の知見などをふまえ、耐震設計の基準となる揺れ・基準地震動を策定している」と主張。「逆断層」については「考えられない」としつつも、「南に80度傾いたケースも想定していて、妥当な評価」だと主張しています。
これに対し、原告は、南に60度から75度傾いた逆断層である可能性も考慮すべきと主張していました。
これらの点について、裁判所は「基準地震動は複数の手法で評価し、最も厳しい結果を採用するもので、その策定方法は合理的である」、また、中央構造線断層帯も「南に傾いた逆断層であると認めることはできない」と、原告の訴えを退けました。
【②火山に対する安全性】
原告側は「過去最大規模の阿蘇山の噴火を想定すると、伊方原発付近にも火砕流が到達した可能性が十分小さいとは言えない」などと主張していました。
一方、四国電力は「調査を踏まえれば、伊方原発の運用期間中に阿蘇で巨大噴火が発生する可能性は十分小さい。また、電源を失っても想定を上回る火山灰に対し、原子炉を冷やせることも確認している」などと反論していました。
この点について、裁判所は「伊方原発の運用期間中、巨大噴火の可能性は十分小さく、四国電力の想定は合理的」と、四電側の主張を全面的に認めました。
【③避難計画】
原告は「伊方原発が日本一細長く、地すべりも多い佐田岬半島の根元に位置し、全国では他に例のない極めて特殊な立地にあることから、これらの特殊性を考慮した避難計画を策定しければならない」などと主張していました。
一方、四国電力は「避難計画は訓練や検証を通じ、改善が図られていて十分な実効性がある」などと反論していました。
裁判では、避難計画の実効性に直接の言及はなく「重大事故などが起きる恐れがあるとは言えない場合に避難計画の不備のみで住民らに危険が生じることはない」との判断を示しました。
全国のトップニュース
【衆議院選挙2026】JNN終盤情勢を徹底分析 野党の大物議員も“追う”展開に…自民「単独過半数」大幅上回る勢い “接戦”78選挙区を詳しく解説【edge23】
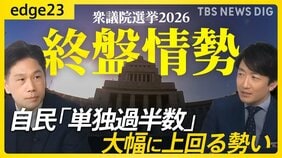
衆議院選挙きょう投開票 期日前投票は6日時点で約2080万人

きのうに続き関東各地で雪 東京23区でも5センチ降雪予想 大学では入学試験の開始時間を繰り下げる対応も

東京でも積雪を観測 日本海側は山陰~北陸中心に記録的な大雪のおそれ 交通障害・歩行中の転倒などの大雪災害に警戒

男子ビッグエアで木村葵来が逆転で金、木俣椋真が銀メダル!「とても重たいです」日本勢史上初の表彰台【ミラノ五輪】

スキージャンプの丸山希が日本勢メダル第1号「すごくうれしい」初出場で銅メダル獲得!【ミラノ五輪】

五輪開催のイタリア鉄道路線で破壊行為 ケーブル切断など3件相次ぐ

ゼレンスキー大統領「米が6月までに戦闘終結要請」 中間選挙見据え圧力か



