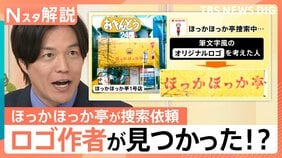岩手の四季をドローン撮影で紹介する「岩手空中散歩」。1200年の歴史を誇る平泉町の「達谷窟毘沙門堂」の秋の風景です。
達谷窟毘沙門堂は建屋と岩壁が一体となっているのが特徴です。延暦20年=西暦801年、征夷大将軍・坂上田村麻呂が蝦夷平定の際、毘沙門天のご加護に感謝して京都の清水寺を模して建て、108体の毘沙門天を祀ったのが始まりとされています。その後、毘沙門堂は2回にわたって焼失し、昭和36年に再建され、現在に至ります。
岩面大佛は高さ33mもの岩壁に刻まれています。
前九年・後三年の役で亡くなった敵と味方の霊を供養するために、陸奥守・源義家が馬の上から弓で彫り付けたと伝えられています。
この大佛は高さおよそ16.5m、顔の長さおよそ3.6m。全国で5本の指に入る大きさです。
「達谷窟」は国指定の史跡に指定されています。
この季節、木々の紅葉が悠久の歴史を鮮やかに彩っています。
全国のトップニュース
中国政府 レアアースの輸出規制強化を約1年間停止 米中首脳会談受け

高市総理が謝罪 生活保護費引き下げの最高裁違法判決を受け 厚労省は引き下げ改定のやり直しを検討

あとを絶たないクマ被害 “200年以上の歴史”老舗温泉旅館にクマ居座り 「寝ている部屋の前に…」経営者家族が語る緊迫の一夜【news23】

フジテレビ取締役が辞任 不適切な経費精算 会食など約60件・約100万円分

相場より2割ほど安い家賃の「アフォーダブル住宅」 東京都が子育て世帯に供給へ 来年度以降に約300戸

タイ国家警察長官「母親は台湾にいる」 タイの12歳少女が都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件

「トライアルGO」「ツルヤ」地方スーパーが続々上陸 関東で“スーパー戦国時代” 生き残りのカギは「店の特色」【Nスタ解説】

「ほっかほっか亭」初代看板ロゴの作者発見⁉自称・考えた人を直撃!“状況証拠”に創業者の見解は【Nスタ解説】