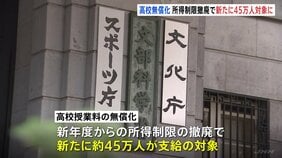クマは約20キロ移動していた?
「クマとまちづくり」をいち早く実践する南町7丁目町内会のあたたかさ。その行動はこの地域だけではなく、ほかの地域にも効果が及ぶかもしれません。
2019年、北海道江別市や北広島市、札幌市にまたがる「野幌森林公園」周辺でクマの目撃や農産物の被害が相次いでいたのですが、実はこのクマ、野幌森林公園で目撃が始まる1か月ほど前に、およそ20キロ離れた真駒内公園で目撃されたのと同じクマだったことがわかっています。駆除された後、真駒内公園に残されていたクマの毛とDNAが一致したのです。
自治体をまたいで無数に広がる「みどりの回廊」。ひとり一人が自分の地域の「まちづくり」を考えることが、北海道全体の安全につながっていくのかもしれません。
町内会長の久保さんは、「本当は行政が草刈りをしてくれたら嬉しい。危険が伴うので、住民に強制はできないし、毎年は難しいとも思っている。あくまで有志で、2年に一度くらいで、続けられればいいかな」とも話していました。
一方で札幌市は「人数や予算の都合で札幌市内のすべての場所を行政だけでやるのは難しく、地域や学生と一緒にやることでクマを意識してほしい」という想いもあるとして、「ここにクマは入ってきてほしくないというラインを一番わかっているのは地域の方。札幌市と地域で話し合ってゾーンを考えていくのもこれから必要なのではないか」と話します。
町内会長と札幌市の話を下川さんに伝え、クマ対策は誰がやるべきだと思うか、聞いてみたところ、考えながらこう答えてくれました。

「行政だけでやっていたら、地域の人が実感を持てないですし、行政プラス地域の方がやるのがいいのかなと思います。今回草刈りに参加していた地域の方に、『クマを見たことがありますか』と聞いたら、見たことがある人がいなかったんです。それでも『ニュースを見て』などで意識を持って参加してくれている人がいる。そういう人が、若い人とか、もっと参加してくれたら、クマ対策は進むのかなと思います」
クマの専門知識を持たない学生が参加する意味
今回の実験では、パネルを使って可視化できた草刈りの効果だけでなく、学生たちの言葉も印象的でした。プロジェクトには、下川さんなど、クマの研究をしている学生のほか、北海学園大学の、クマの専門知識を持たない学生たちも参加してくれています。HBCと北海学園大学で作る「もんすけラボ」(※1)のメンバーの中で、「クマ対策に興味がある」と手を挙げてくれた学生たちです。

彼らは下川さんらにクマの生態について質問しながら学んでいき、実験に際して、「大人目線だけではなく、子ども目線でも考えたい」と地域の方の動機に寄り添った提案をしたり、「専門的な調査は下川さんたちに頼る分、草はたくさん刈ります!」と意気込んでザクザク刈ったりと、自分にできることを探して取り組んでくれています。
クマについて「知らない」ところから、「知る」段階、「行動する」段階へと、楽しそうに進んでいく姿を目の当たりにして、こんなふうに前向きに「じぶんごと」にしていくことが、クマ対策のカギなのかなと、気づかせてもらいました。
草刈りだけで、クマの出没がゼロになるわけではありません。それでも、ただ怯えるだけではなく、私たちには「できることがある」と、前向きに考えてみませんか?
これから「クマとまちづくり」プロジェクトでは、学生自身も気づきをSitakkeで発信してくれます。ぜひ一緒に、「できること」をひとつずつ、見つけていきましょう。
※1:もんすけラボ
HBCと北海学園大学が2019年に開設した若年層向け協創型メディアシンクタンク「北海道次世代メディア総合研究所」の愛称。学生・教員とHBCスタッフがアイデアを出し合い、実践活動につなげています。
文:Sitakke編集部IKU
2018年HBC入社、報道部に配属。その夏、島牧村の住宅地にクマが出没した騒動をきっかけに、クマを主軸に取材を続ける。去年夏、Sitakke編集部に異動。ニュースに詰まった「暮らしのヒント」にフォーカスした情報を中心に発信しています。