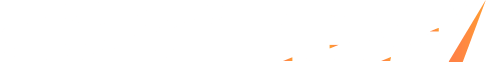ターニャと過ごす最後の時間
いつものように、重厚な木のドアをノックすると、ターニャがドアを開けて、少し寂しそうな表情を浮かべながら、こう呟いた。
「ハルオ、最後の日に来てくれてありがとう」
返す言葉もなかった。
「淋しくなるわ…じゃあ、元気でね、ハルオ」

会話は短く簡潔だった。最後に、彼女とお互いの左の頬を重ねて頬ずりをした。彼女の温もりを肌で感じるとともに、彼女の深い悲しみも頬をつたう冷たい涙で感じた。
自分は、ターニャにどれだけ助けられただろうか。全く色のない灰色のシベリアの生活に彼女は彩りを入れてくれた。暗い捕虜生活にまばゆいばかりの光を照らしてくれた。

つらいことも、悲しいことも、苦しいことも、彼女と会っている時だけは忘れさせてくれた。それが春男さんにとって、どれだけの救いになったことだろうか。ターニャがいなかったら、自分はどうなっていたのだろう。生きる希望を失い、絶望の中で彷徨っていたかもしれない。
その後の春男さんの人生を振り返っても、あの最も苦しい時に咲いていた1輪の花に感謝しかなかった。それは80年近くが経過しても決して色褪せることはなかった。