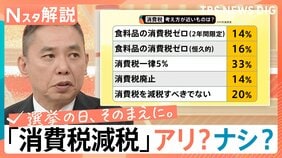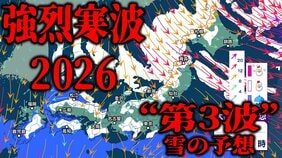道路隧道じゃなくても“隧道”を掘ることはできるのでは…

国道471号から旧道を進むと、廃道区間に現れたのは昭和30年竣工の「楢尾(ならお)トンネル」。
当時はこの場所に道を造っても利用者数に対して工事費用が見合ってないという理由で、県から補助金がおりず実現しなかったそう。一体、どのようにして造ることができたのか?
(道マニア・石井あつこさん)
「正攻法では車道を造ることが叶わなかった。しかし、道路隧道じゃなくても隧道を掘ることはできると気づき、田んぼを開くことにした」

人が通るための隧道では補助金が出なかったため、利賀村の有識者は農業の補助事業に着目して開田計画を立て、百瀬川から農地への水路として隧道をつくる案を提出。
昭和28年にその計画は承認され、2年間の工事を経て長さ800mの水路隧道が完成。その後、村の単独事業として水路の上に歩道を設置することで、念願の道路が完成しました。
(道マニア・石井あつこさん)
「田んぼを作る大義名分を得て穴を穿つことに成功した。この水路ができたおかげで美しい田んぼが広がり、さらに人々が往来でき、小学生が安心して通学できる人道隧道を開通させた」
昭和63年にはすぐ南に「新楢尾トンネル」が開通。「楢尾トンネル」は廃道となり、現在は立ち入り禁止となっています。