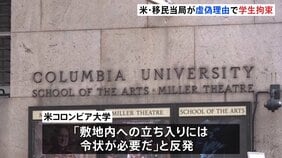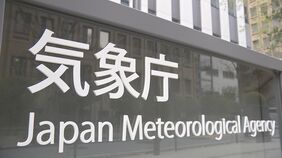■りんご王国青森県弘前市だからこそ生まれた桜の管理方法「弘前方式」
「弘前方式」は弘前公園内で起きたある出来事がきっかけで生まれたといいます。
その出来事が起こったのは今から71年前の1952年。この時、弘前公園では明治時代に植えられていた桜の木々が昭和に入ると共に徐々に衰え始めていったといいます。
こうしたなか、枯れ枝が落ちてくるのを防ごうと現在の弘前市公園緑地課の前身である弘前公園管理事務所の初代所長であった工藤長政さんは職員に弱った桜の木の枝の剪定を指示。しかし、指示を受けた職員のうち実家がリンゴ農家だった職員は弱った枝の部分ではなく、まだ生きている幹の部分からばっさりと剪定をしてその根元に肥料を入れたといいます。
当時は桜はとても繊細な樹木で、切り口から病気が入りやすいため、こうした強い剪定はありえないと考えられていた時代。工藤所長は怒りをあらわにして職員に注意をしたほか、様々な研究者からはこの剪定方法が批判され、それが新聞などに取り上げられるなどして「弘前公園の桜は10~20年後にはなくなる」と言われたといいます。
しかし、その剪定から1年後。切り落とした部分からは新たな若芽が芽生えて樹勢も徐々に回復。この光景を目にした工藤所長は、桜とリンゴが同じバラ科でもあることから自らもリンゴ農家に教えを請いながら研究を重ね、弘前独自の管理方法を育んでいきました。こうして、美しい花を咲かせる桜が100年以上生きることのできる現在の「弘前方式」が生まれました。


■60年以上手間をかけ守ってきた美しい桜
切り落とした部分から新たな若芽が芽生える桜の原理を利用することから「若返り」を基本理念としている「弘前方式」。リンゴ栽培から倣った「剪定」、「施肥」、「薬剤散布」の3つの基本的作業と根の病気に対する積極的な外科手術や幹から伸びる不定根の保護、土壌改良などを掛け合わせることで進化してきたこの桜の管理方法は、現在も公園緑地課の職員に受け継がれています。
チーム桜守の海老名さんは、これらの作業のなかでも特に「施肥」は大切な作業だと語り、肥料を与えることで桜の木が元気に生育するからこそ、老木になってもしっかりと剪定することが出来て毎年ボリュームのある花を咲かせることにつながっているのではないかといいます。


「やっていること自体はそんなに難しくなく特別な技術が必要なわけでもない。全国から視察も来てくれるが、やろうと思えばどこでもできる。ただ、桜は1年のうちに1週間~10日間のみ咲く花を愛でるもの。それに対して1年を通して肥料や薬剤散布などの手間をかけることを弘前市では60年以上続けられているからこそ老木もボリュームのある花をつけるし、すごいのだと思う。」
今年は4月21日から5月5日まで行われることが決定している弘前さくらまつり。
弘前公園の桜の木々は今年も公園緑地課の職員と桜守たちからの多く愛情を受けて見事な花を見せてくれるでしょう。