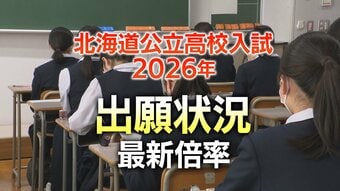私のふるさとである滝川に、ひっそり建つ記念塔があります。
堀颯月記者
「空知の滝川です。今は草木が生い茂っているこの土地ですが、戦時中には、とあるものを作るための大きな工場がここにありました」
東洋一と呼ばれた「北海道人造石油 滝川工場」です。
1930年代後半、国際情勢が緊迫し、日本とアメリカの関係が悪化。石油をアメリカからの輸入に頼っていた日本は、軍用機の燃料などに使う石油の自給をめざします。石炭から石油をつくる=「人造石油」の工業化をはかったのです。
滝川の郷土史を研究してきた白井重有さんです。私に現存する唯一の「人造石油」を見せてくれました。
滝川市美術自然史館 初代館長 白井重有さん(88)
「これは人造石油会社の滝川工場でつくられた石油の原油です」
1938年、石油を確保するため設立された国策会社「北海道人造石油」。滝川の工場でつくられた現存する唯一の「石油」があります。
白井重有さん
「これは初めて合成に成功して、油が出たという記念すべき写真です」
堀颯月記者
「この石油は何から作られましたか」
白井重有さん
「石炭です」
石炭を蒸し焼きにして、水性ガスを加えて混合ガスを発生させ、触媒反応で液化させる当時では最先端の技術です。
現在の金額でおよそ1兆円をかけ、滝川に札幌ドームおよそ30個分の巨大な工場が建てられました。
白井重有さん
「全国各地から科学者の方々がみんな集まった」
堀颯月記者
「従業員の数は」
白井重有さん
「2000人です。戦争と一緒に工場も拡張していった」
1942年に「人造石油」の生産に成功し、戦地へと出荷されます。
白井重有さん
「石油の一滴は血の一滴と言われた時代、死に物狂いで石油を作った」
かつて工場で働いていた目黒教子さんです。
工場で働いていた目黒教子さん
「親の店手伝ってもね給料くれないからね娘心だからね。給料もらえるところにいきたくて、親に内緒で願書出したら合格したんです」
1941年から3年間、労務管理などを担当し、作業員たちを支えました。
目黒教子さん
「一つ爆弾落とされたら終わり。なんせ戦争中ですから。やっぱりね、こうやって平和に暮らせるのも先人の方の色々があって、こうやって滝川も従業員がいたから町も発展した。人造石油のおかげだというのは忘れてはいけない」
しかし、終戦を機に「人造石油」の生産は停止。その後、民間会社が引き受けましたが、巨大な工場に見合った業績を上げられず、1952年に経営破綻しました。
白井重有さん
「(工場が)大きいがゆえに再建が難しかった。ただこの技術が日本国中に人と一緒に散っていったことが、滝川としては悲劇だったかもしれないが、日本の化学工業にはプラスだったと私は信じている」
人造石油の工場の一部は、現在、陸上自衛隊・滝川駐屯地の庁舎として、その姿を残しています。
科学技術を平和のために使うのか、戦争のために使うのか、私のふるさと滝川で作られた「人造石油」は、問いかけています。
注目の記事
選挙戦の裏で起きた動画の応酬「足組みクリームパン動画」に対抗 森下氏の過去動画を拡散した立憲・奈良市議「有権者への判断材料を示したかった」と主張【衆議院議員選挙より】

【南海トラフ巨大地震】9分で津波到達も「逃げるより家にいた方が…」 500年前に“究極の津波対策”を決断した集落が三重に

住民の血液から高濃度PFAS アメリカの指標の110倍を超える値も 飲用井戸から全国最悪のPFASが検出された地域で 今必要なことは…? 広島

客の指示を無視して警察へ直行…マンボウタクシーの運転手 常連客救った‟とっさの判断‟と行動力に感謝状

「110円でゴミ出し」 もOK? “破格”の家事代行サービス 利用者が急増中…お墓参りは買い出し~清掃まで合わせて1万円

「車のフレームにぶつけた、たった1か所の傷。それが致命傷でした」中学2年生の娘を事故で亡くした母親が語る「命の尊さ」【前編】