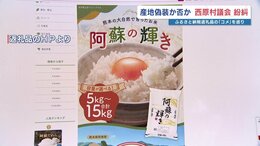「食の匠」から郷土料理について学ぼうという教室が5日、岩手県軽米町で開かれました。参加者が作ったのは、地域の食材を生かした伝統食「てんぽ」と「生麩」です。
この教室は、地域の食文化を受け継いだ岩手県認定の「食の匠(たくみ)」から、郷土料理の知識と技術を学び後世に伝えようと開かれたもので、「野菜ソムリエ」の団体に所属する10人が「てんぽ」と「生麩」作りに挑戦しました。
「てんぽ」は、昔から県北地域で多く生産されてきた小麦粉に水と塩を加えて生地にし、型ではさんで焼いたものです。「てんぽ」作りの講師は町内在住の「食の匠」、笹山ひとみさんです。
(笹山ひとみさん)
「冬になるとよくおばあちゃんが作ってくれて食べていた。小麦粉と塩を少しとゴマとクルミできょうは作った。とてもシンプルだが、素朴で味わいのあるおせんべい」
一方の「生麩(なまふ)」は、「てんぽ」と材料は同じですが、作った生地を水につけながら10数分かけてもみ洗いすることで弾力を生み出し、茹でて刺身のようにして食べます。
(「食の匠」 大崎和子さん)
「代々、嫁に来たときから作っている。昔はお盆に作った。いつも流れでやっているからコツが(言葉に)出てこない」
きょうは県北地域の鶏肉や野菜、果物を使った料理も作られ、講師と参加者全員で地域食材を生かして作った品々を味わいました。
(参加者)
「自分の手をかけて時間も使ったので倍以上おいしく感じる。もともとがおいしい」
(野菜ソムリエコミュニティいわて代表 宮田恵さん)
「レシピを見ただけだとわからない。手元で見る、技術を実際に見て、食べて見なければわからない味や食感もある。勉強になった。自分たちで生産して食べるという岩手で普通に行われてきたことは今後もすごく大事になってくる」
食の匠から学ぶ料理教室は今後も県内各地で開かれる予定です。