遺族に重く伸し掛かる思いはまるで「鉛の球」

今年7月。母・みかさん(仮名)は、ある集会に参加するため神戸へ向かいました。息子の遠征で度々行っていた県外を訪れるのは3年ぶりのこと。
その移動中、みかさんの目からは度々涙がこぼれ落ちました。
母・みかさん(仮名)
「飛行機の中でもずっと泣いていて…。今日ここに来る目的ってなんか違うんだよなって。でもやっぱり神戸に行くって決めたからには、しっかり向き合わないといけない。つらいけど、つらさを何かの力に変えるものがあるんだろうなって思って」
息子のために歩みを進めたい思いと、息子がいない喪失感に苛まれる思い。街の風景を見ながら、みかさんはこう語りました。
母・みかさん(仮名)
「なんかね重なるものが、いろんな目に映るものが。さっきも電車の中で学生さんを見ていると、息子と年齢が近いんだろうなとか。一緒に成長を見ていきたかったのに、こんなに早く逝っていってしまうなんて。こういう時でも、親として何かできるものとか、乗り越え方とかを“皆さん”に聞けたらなって思って」
必死で自分を奮い立たせて、みかさんが向かったのは、学校での事故や事件などによって子どもを亡くした遺族が集まる『全国学校事故・事件を語る会』でした。
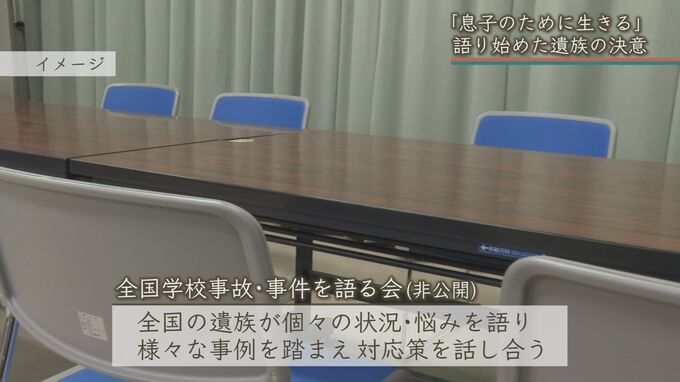
この会は非公開で行われ、全国の遺族が個々の状況や悩みを語り、弁護士らも参加しながら様々な事例を踏まえ対応策を話し合います。
会を設立した一人、自身も自死遺族の内海千春(うつみ・ちはる)さんは、遺族の思いをこう代弁します。
全国学校事故・事件を語る会 事務局 内海千春さん
「うちの息子は1994年9月に教員の暴行の直後に自殺しました。当時本当にぼろぼろになりました。子どもが亡くなったこともぼろぼろだし、もう一つは、僕、その時は、現職の中学校の教員だったんです。周りはみんな敵になるし、子どもは亡くす、未来も無くなる。鉛の球、鉛を飲んだような気持ちっていうか、それは常にあります」
「受け入れられない自分がいるんだけど、それに折り合いをつけて生活ができるようになるまで、自分が変わらざるを得ないんですよね。そのためには七転八倒します、だからみんなのたうち回りながら、苦しんで苦しんで、その人なりの向き合い方を模索していくというのがあるみたいです」










