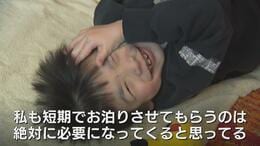この春開設された立命館アジア太平洋大学サステイナビリティ観光学部の学生たちが大分県臼杵市の食を広く認めてもらおうと研究を開始しました。
6日は20人余りの学生がみそとしょうゆの生産現場を訪れ、製造過程やリサイクルの仕組みを学びました。臼杵市は2年前、ユネスコの食文化創造都市ネットワークへの加盟が認められ、食をいかしたまちづくりを進めています。
(学生)「作る過程を見ることで廃棄を出さないことが当たり前になっているというところで考え方が変わった」
また無農薬や有機栽培で育てる「ほんまもん農産物」の生産農家にも足を運びました。
(学生)「圃場が全部緑な感じが初めて見た感心しました」「自然な形で育てることも植物をちゃんと育てるという部分に関してはすごく重要なことなのではないか」
学生たちはグループ別に発酵や経済、健康など6つの視点から食と文化の関係性、「ガストロノミー」を分析していく計画です。
(APUサステイナビリティ観光学部・須藤智徳教授)「臼杵の食文化のサステナビリティを評価していきたい。将来どういう形で残っていくべきか最終的にまとめていきたい」
SDGsの観点からも注目される臼杵の食文化。須藤教授は今後、研究の成果をシンポジウムのような形で多くの人に伝えたいとしています。