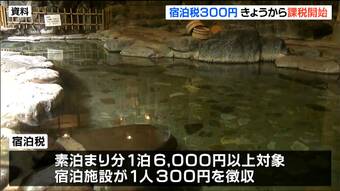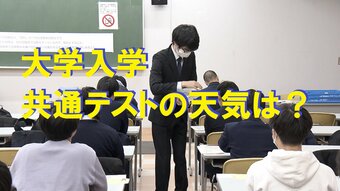女性に多い「寒暖差疲労」
「寒暖差疲労」に詳しい久手堅司医師は、特に女性や、あまり体を動かさない人が発症しやすいと言います。
せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司院長:
「女性は筋肉量が少ないし、あとは一番の女性の不調が出やすい理由というのは、どうしても性周期でホルモンのバランスが乱れるので。どちらかというと運動して発汗が多い成長期の女性は(寒暖差疲労は)少ない」
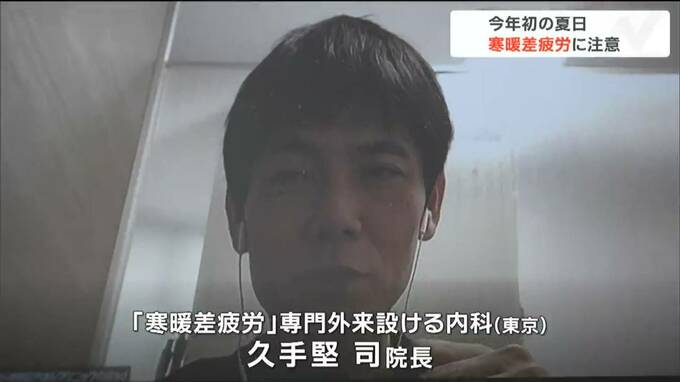
仙台は11日の平年の最高気温と最低気温の差は9度以上あり、一年で最も大きいため、県内は今、特に寒暖差疲労が起きやすい時期と言えます。
せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司院長:
「まずやっぱり天気予報をしっかり見てもらうことが大切かなと。体温調節のしやすい服を一枚持ってるかどうかで変わってくるので。女性だったらカーディガンやスカーフを使ってもらって調節するのが大事かなと」
久手堅院長によると、服装調節以外にも、暖かい食事や入浴などで体を中と外の両方から温める、それから脳と腸の働きは自律神経でつながっているので、発酵食品をとるなどして腸内環境をよくすることも寒暖差疲労の対策になるということです。