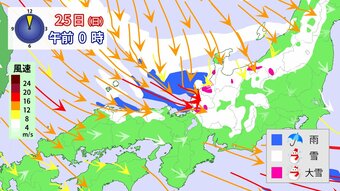典型的な資金繰り破綻でした。アメリカ・カリフォルニア州のシリコンバレーバンク(SVB)が、まるで突然死のように、経営破綻しました。スタートアップ企業やベンチャーキャピタルなどに積極的に融資していた、全米16位の銀行でした。次いで12日には、仮想通貨(暗号資産)企業との関係が深かった、全米29位のシグネチャーバンクも破綻しました。
バイデン政権は預金全額保護で不安払拭
相次ぐ銀行破綻は、「経済好調」で「インフレだけが心配」と思われたアメリカ経済を、一気に危機モードに変えました。
バイデン政権と金融当局は、12日になって、これ以上の連鎖破綻を防ぐために、預金の全額保護を打ち出し、不安払拭に努めています。ルールであるはずのペイオフを実施しないのは、政権の危機感の表れです。
25万ドル(日本円で3400万円)までの預金保険の保護の対象を、思い切って全額にしたことは、一定の安心感を生んではいるものの、中小銀行の株価が急落するなど、なお予断を許さない状況です。
SVB破綻は融資先の焦げ付きが原因ではない
発端となったシリコンバレーバンク(SVB)の破綻は、通常の銀行破綻に見られるような融資先の焦げ付きが、全くと言っていいほど見られなかったことが、最大の特徴です。
不良債権問題が原因ではないのです。では、なぜ倒れたのか。預金が急速に引き出される一方、持っていた資産が金利急騰で目減りして、資金がショートしたからに他なりません。
SVBの預金は、2019年から2022年にかけて3倍にも膨れ上がっていました。顧客であるシリコンバレーの新興IT企業が、コロナ禍の金融緩和環境でベンチャーキャピタルなどから多くの資金集めに成功し、メインバンクであるSVBにひとまず預金したからです。ゼロ金利時代にはITベンチャーの企業価値はより大きく評価され、現に巣ごもり需要もあって成長が見込めたからです。
預金が膨れ上がったSVBは、それに見合うほど融資は拡大できないので、アメリカ国債や住宅ローン担保証券(MBS)で運用していました。いわば普通の債券投資です。
預金減少と債券損失による破綻
ところが2023年に入り、インフレ退治のために中央銀行のFRBが利上げを開開始すると全く違う風景になりました。しかも、1年で4.5%もの歴史に例を見ない激烈な利上げです。債券価格は急落し、巨額の評価損が発生しました。
その一方で、急速な利上げによって資金調達環境が一変したITベンチャーは一斉に預金を取り崩し始めました。金利高騰で企業価値が急速に小さく評価されるようになったITベンチャーは加速度的にキャッシュを必要としたからです。
SVBは預金払い戻しのために、損を承知で、持っていた国債などの債券売却を迫られました。売却すれば、評価損は現実に損失として確定します。そうなれば、あとは信用不安の連鎖です。更なる預金流出に耐えられず、破綻に至りました。
SVB固有の事情もあるが、金利急騰が大きな要因
では、今回のSVBの破綻から何が見えるでしょうか。確かにSVBが新興IT企業などとの関係が特別に深く、預金量の変動があまりに大きかったという意味では、特別な例だったと言えるでしょう。その意味で、SVB破綻が金融危機に連鎖する可能性が低いという見方には、一理あります。
しかし、その一方で、急激な金利上昇が、世界で一番安全なはずのアメリカ国債や債券保有に大きな評価損を生じさせていることは事実です。
SVBほどでないにしても、アメリカの金融機関は、普通に多額の国債やMBSを保有しています。もっと言えば、融資先が拡大しない日本の地方金融機関だって、アメリカ国債を始めとする外国債券を買っています。そして、その量に応じて評価損を抱えているのです。
マネー逆流が金融危機を招くリスク
また、局所的なマネーの逆流も大きなリスクです。今回のSVB破綻劇では、主力顧客である新興IT企業をめぐる資金の逆流が、銀行破綻の引き金を引いた形ですが、金利の急騰によって、局所的に激しい資金の逆流が起きているところは、恐らく他にもあるはずです。
さらに、信用不安の情報があっという間に、巨額の預金流出につながるネット時代のリスクも見逃せません。今回の破綻劇ではSNSでの情報の拡散も、預金流出を加速させたと言われています。情報も、取引も瞬時にデジタルで行える時代の金融破綻劇は、かつてとは全く異なるスピードが進むことも、今回わかりました。
今回の銀行破綻が金融危機につながらないように、各国の金融機関や当局はこうしたリスクチェックを直ちに行う必要があるように思います。
歴史的に見てアメリカの金融引き締め局面では大体、経済危機が発生しています。今回は引き締め速度がかつて例を見ないほど急速なだけに、なおさら注意が必要な局面に入って来ました。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)