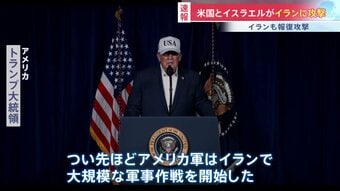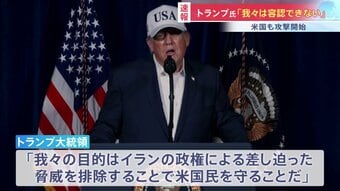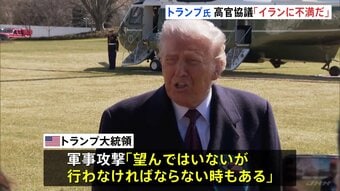去年異例の3期目に突入した中国・習近平政権が困難に立たされている。新型コロナ感染大爆発。GDPの成長が目標を大きく下回る経済の停滞。さらに人口の減少。
打ち立てた目標が次々と崩れてゆく習近平氏の舵取りを読み解いた。
アメリカの“デカップリングの強化”と中国の“ノー・デカップリングの提唱”
一人でも感染者が出ればロックダウンに外出禁止といった徹底したゼロコロナ政策から一転、今度は全く規制無しの野放し状態による感染爆発。とにかく極端な中国だが、コロナは急拡大ゆえにピークアウトも早く、北京など都市部では日常が戻りつつあるという報道もある。
しかし、経済の減速は深刻だ。中国のGDPの実質成長率は2010年代に入り頭打ちながら高め安定をキープしていた。これがコロナで一気に下落したものの2020年持ち直した。その後コロナ前水準で安定することを見越して去年の目標値は5.5%と設定していた。ところが今週発表されたGDP成長率は3%だった。
元駐中国大使 宮本雄二氏
「習近平さんが“2050年までにアメリカに追いつくんだ”っていう大目標を掲げていた。そのシミュレーションのベースとなる経済成長のシナリオが変わってくるんじゃないか…。おそらく中国のシミュレーションでの数字はこんなに悪くなかったと思う。(中略~これからは)労働生産性を上げていくしかない。労働の質を高めなければならない。質を高めるためには西側、EUとかアメリカとか日本ときちんと関係を作っていかなきゃ労働生産性の向上はない」

これまでの中国では人海戦術による大量生産がベースだったが、今年発表された中国のデータでGDP以外にも衝撃的な数字があった。2022年の統計による人口が61年ぶりに減少したのだ(14億2589万人)。出生数は過去最少だった。今年中にはインドが人口世界一位となる見込みだ。さらに生産年齢人口は今後10年間で9%減少するという。つまり働き手が減るのだ。この現状を打破する労働生産性の向上には欧米との関係が重要だというが、アメリカは逆の政策を打ち出そうとしている。デカップリングの強化だ。
米下院の中国特別委員会では、「中国による個人情報・雇用の窃取防止」「医薬品・レアアースの中国依存脱却などの調査・政策提言を行う」などが決まった。マッカーシー下院議長は「我々はこれ以上中国に依存しない」と述べている。

一方、中国はヨーロッパに対し「ノー・デカップリング」に同意するよう主張している。フランス・マクロン大統領は今年早々にも訪中しデカップリングに反対を表明するのではないかと、イギリス・フィナンシャルタイムズは伝えている。またドイツは去年既にショルツ首相が「中国は重要な経済・貿易パートナー」とし、デカップリング反対を明言している。
日本総研 呉軍華 上席理事
「今後の成長には生産性の向上が不可欠。『ノー・デカップリング』の提唱はそのことへの示唆。日本も含めた欧米諸国との交流、カップリングではじめて生産性は向上するという問題意識を中国は持っている」
ヨーロッパにおいて中国は経済面でパートナーとしてのポジションを確立している。日本も同様だ。やはり問題は米中関係ということになる。
拓殖大学 海外事情研究所 富坂聰 教授
「米中は国と国の関係が凄く悪い。ただ産業界はデカップリングの強化にものすごく大きく動くかっていうと、現実的にはある程度の関係は保つんじゃないかと…。それより中国経済で心配なのはコロナでダメージ受けたの消費。中国は実は、経済の構造転換の中で消費を経済の中心に置いてきた。この転換のど真ん中にコロナが来た。これは明けても戻らないんじゃないかっていう心配。これがかなり懸念されている…」
中国経済の不振。その中心が消費の落ち込みであることは世界経済にとって大打撃であると堤伸輔氏も懸念する。
国際情報誌『フォーサイト』元編集長 堤伸輔氏
「アメリカから見ても中国は第3位の輸出国。アメリカがデカップリングする前に中国経済が減速して結果的に世界経済に大打撃を与えてしまう。半導体などはともかく一般商品をデカップリングしたら、その返り血は世界全体が浴びてしまう」
インドに抜かれたとしても中国は14億人の巨大市場なのだ。言うなれば、中国経済は世界の誰にとっても他人事ではない。