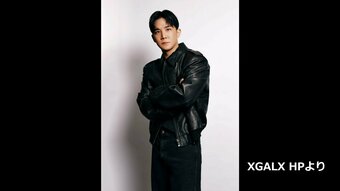■異次元緩和の罪。不自然な政策のツケはこれから
日銀の金融政策は正常化に向けてどのような道をたどるのだろうか。黒田総裁が強調したのは利上げの否定だった。「今回の措置は、市場機能を改善することで金融緩和の効果が企業金融などを通じてより円滑に波及していくようにする趣旨で行うものであり、利上げではありません」

欧米が相次ぎ利上げする中、日銀が長期金利を低く抑えたため市場に歪みが高まったので、改善して市場機能を取り戻すのが目的で利上げではないとしている。
――黒田総裁がこれは政策修正ではない、利上げではないというのはなぜか?
東短リサーチ 加藤出社長:
「政策変更の一歩」だと言ってしまうと、マーケットはどんどん走り始めてしまう。次の10年金利の引き上げはいつか、マイナス金利の解除はいつだろうかと走り始めてしまうので、「市場機能の改善」と言い続けるしかありません。
そもそも黒田総裁は変動幅の拡大には否定的だった。9月の会見では「プラスマイナスの0.25%をもっと幅広くしたら、明らかに金融緩和の効果を阻害すると思うので、そういうことは考えていない」と述べていた。
東短リサーチ 加藤出社長:
今まで金利引き上げの必要はないと言ってきた手前、ちょっと理由をずらさないと整合性の点で問題があります。特に日銀政策委員会内の若田部副総裁らリフレ派の委員たちは「金利引き上げ」という言い方にするとなかなか納得できない。
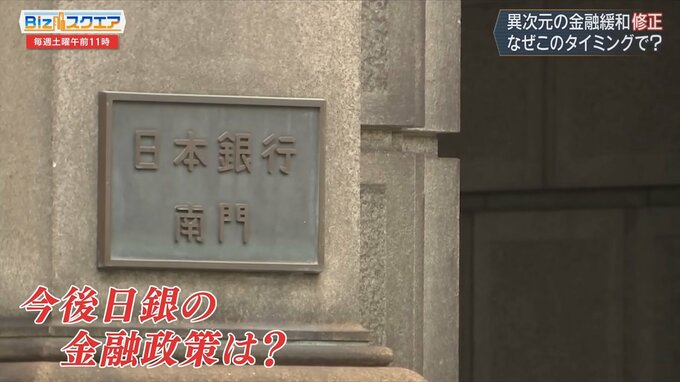
東短リサーチ 加藤出社長:
FRB(米連邦準備制度理事会)の利上げが5月ぐらいまでは続くと勘案すれば、来年の4月から夏前までの間に10年金利の上限がまた引き上げられたり、さらには10年金利の誘導自体を数字を示して誘導するのをやめたり、マイナス金利政策を若干のプラス金利に戻すというような変更が来年夏までの間に予想されます。
――日銀が金融市場の最大の不安定要因になっていくということでは?
東短リサーチ 加藤出社長:
10年金利を固定するというのは極めて不自然な政策で、他の中央銀行はやっていません。大変出口が難しいものを6年も続けてしまったので、それなりのツケというものは残念ながら出てしまいます。
金利を動かすということを事前に言えないのは、その通りだろう。しかし、決めた結果については国民にきちんと説明する責任がある。企業活動にも国民生活にも直接影響を及ぼすものだからだ。それでも、政策修正と言えば市場の圧力に抗しきれなくなるから言わないというのであれば、この異次元緩和の罪のなんと大きいことか。異次元緩和の修正自体は経済の正常化という意味で正しい方向なのだろうが、今回の不意打ち修正劇を見ると、今後も不意打ちが続く、つまり完全な出口までには相当なショックを我々は覚悟しなければいけない。
(BS-TBS『Bizスクエア』 12月24日放送より)