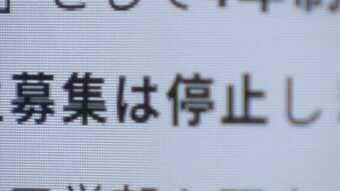◆世界初の発見! 4種類めの新種

今回の企画展では、世界で初めて、3年前に沖縄県で見つかった「ウグマウナギ」の子供の標本も展示されています。
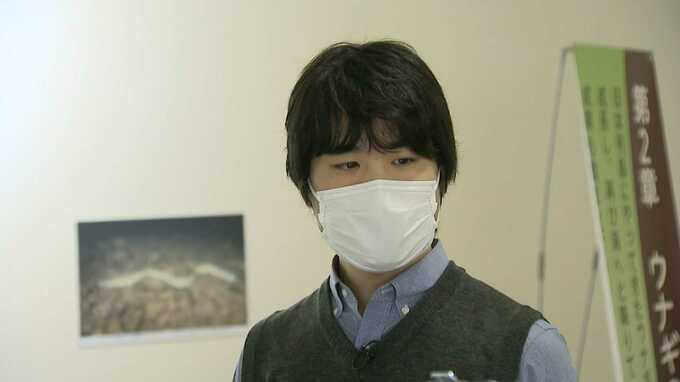
いのちのたび博物館 日比野友亮学芸員「国内には合計で3種類のウナギの仲間が元々いるということがわかっているんです。ところが、もう1種類いたと2020年に(論文に掲載されて)分かったわけです。大きく成長したものは国内では誰も採集したことがない。皆さんが血まなこになって探しているところ」
ウナギの仲間にあたる、ウツボも新種が見つかりました。褐色の丸い模様が「タピオカ」に見えることから「タピオカウツボ」と名付けられました。

訪れた人「ウナギの神秘的な生態にびっくりしました」「おなかを上に出して寝ちゃってるのが、ちょっと笑っちゃいますね」
◆卵からの完全な養殖にも成功
ウナギの生態が少しずつ明らかになるとともに養殖の技術も進んでいます。こちらのウナギのかば焼きは、卵から稚魚、大人のウナギに成長するまで全て人の手を介して育てられた「完全人工生産」のウナギです。現在、ウナギの養殖には川などで捕まえた天然のシラスウナギが使われています。漁獲量が安定せず、資源の枯渇や価格の高騰も懸念されています。鹿児島市の新日本科学は2017年、世界で初めて地上でのシラスウナギの生産に成功。今年、完全養殖した食用のウナギ100尾ほどを育てることに成功しました。

新日本科学 永田良一社長「今後の課題は、数です。大きなスケールで作れるように、海でできるようになると大量生産に一歩近づくと思う」
絶滅危惧種に指定されているウナギ、日本の大切な食文化を守っていくためにも、生態の研究は大きな意味を持ちます。