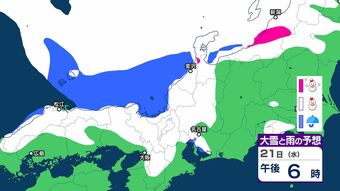話題の「ジェネリック〇〇」という概念からみえる無印良品の本質
無印良品のコスメが急成長したのは、いわゆる「ジェネリック◯◯」に見られるような「本物によく似ていて、価格が安い代替品」として消費者へ広がったことが大きな理由です。デパートで売られている高級コスメブランド(デパコス)と同等の品質を持ちながら、手頃な価格で提供する戦略が功を奏したのです。
無印良品のデザイナーの一人である原研哉さんが語っている「エンプティネス(空っぽ)」という概念が、ブランドを形作るDNAの一部となっています。原さんは日本の神社の「屋代(しろ)」を例に挙げ、日本文化が持つ「空っぽ」は「満たされる可能性そのもの」と説明します。四本の柱と屋根だけの空間に神様が宿るように、無印良品の商品も「空っぽ」であることでユーザーの自己表現の場となるのです。
このような特性を持つブランドを、「余白型(キャンバス)ブランド」と呼ぶことができます。無印良品の商品はシンプルで自己主張が少ないため、使う人が自分の生活の文脈で意味づけをしやすく、SNSなどでの発信がしやすいという特徴があります。無印のレトルトカレーもコスメも、ブランドとしては「空っぽ」であり、その部分を消費者が自分自身の表現で埋めていくのです。
UNIQLOと無印良品に共通するグローバル成功の秘訣
この「余白型ブランド」の概念は、無印良品だけでなく、ユニクロにも当てはまります。ユニクロは2025年8月期の国内売上高が前期比10%増の1兆300億円前後となり、初めて1兆円を突破。グローバルでも売上収益は前期比10%増の3兆4000億円に達し、海外事業の売上比率は55.2%と過半数を占めるに至りました。
ユニクロも無印良品と同様に「余白性」を持ったブランドといえます。特に「UT」シリーズでは、世界中のアーティストやキャラクター、ポップカルチャーとコラボレーションすることで、ブランド自体がキャンバスとなり、多様な表現を受け入れています。
日本発のブランドに「余白性」が多く見られるのは偶然ではないようです。イギリスの研究者ラファウ・ザボロフスキ博士は、日本の音楽文化「ボカロ」について、「初音ミクは空っぽのうつわ(エンプティコンテイナー)で自分の感情を投影できる」と分析しています。彼は「日本の歴史や文化に根ざす"余白"はとても大きく、どう埋めるかは個人・世代・地域によって異なる」と指摘し、これが世界的にも珍しい特徴だと述べています。
日本発「キャンバス・ブランド」が持つ世界的な可能性
「余白型ブランド」は、LEGOやマインクラフト、ロブロックスのようなユーザーの創造性を活かすプロダクトにも見られます。これらはいずれも業績を大きく伸ばしており、LEGOは10年で売上が2倍以上、マインクラフトは販売本数が約4倍、ロブロックスは売上が10年で80倍近くになっています。
日本のアニメやゲームキャラクターが世界中で愛される背景にも、この「余白性」があります。人種も国籍も特定されていないファンタジーの世界観は、世界中の若者がそれぞれの文化や価値観を投影できるキャンバスとなっているのです。2025年にはネパールの反政府デモの際に、若者たちが日本の漫画「ワンピース」の海賊旗を掲げるという象徴的な出来事もありました。
無印良品とユニクロに共通する「余白型ブランド」のコンセプトは、日本発のブランドが世界で成功するための重要な鍵となる可能性があります。ユーザーの創造性や自己表現を受け入れる「空っぽのうつわ」としての特性が、グローバルな多様性の中で強みとなっているのです。
<コムギコ:資本主義をハックしろ!!>
毎日ニュースを100本を読むビジネス系VTuber兼リサーチャー・編集者のコムギ(comugi)が、日々の経済にまつわるニュースを解説するビデオポッドキャスト。本記事は2025年10月16日配信『無印良品カレーはなぜ人に勧めたくなるのか?:日本の「余白型ブランド」が世界を制する』から抜粋してまとめたものです。