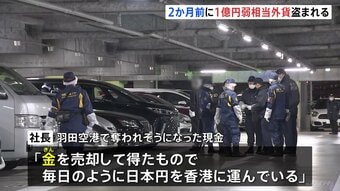相次ぐリチウムイオン電池による火災。こうした事態を受け、政府は、来年度にもモバイルバッテリーなど、小型家電の回収を義務化の対象に加えることで検討に入りました。
燃えにくい次世代型バッテリーなど、モバイルバッテリー対策について見ていきます。
内部に燃えやすい「電池」と「液」で、よりリスクの高い状態

南波雅俊キャスター:
モバイルバッテリーの火災はニュースなどにもなっていて、燃えなくても熱を帯びて膨らんできたという経験をした人もいるかもしれません。
燃えにくい次世代型バッテリー、あるいはモバイルバッテリーの対策について見ていきます。
これまで多く使われてきたモバイルバッテリーの発火はなぜ起こるのかを、関西大学化学生命工学部の石川正司教授に聞きました。
石川教授によると、モバイルバッテリーの内部には▼「リチウムイオン電池」と▼「電解液(有機溶剤)」が入っているということです。
「リチウムイオン電池」は、モバイルバッテリーに使われていますが、電池自体が不安定な素材で、燃えやすいそうです。
電池内部の「電解液(有機溶剤)」は、灯油やシンナーなどと同じ石油類だそうで、60℃~80℃で引火します。
燃えやすい「リチウムイオン電池」に加えて、「電解液(有機溶剤)」も引火しやすいので、さらに発火リスクが高まるということです。
燃えてしまう要因には、以下のような理由があります。
●暑さ・熱
炎天下のなかに置いておくと、熱がこもり、危険が高まります。
●ダメージ
落とすなどの衝撃を受けると、その部分が破損します。内部も破損してしまい、ショートして燃えてしまうリスクが高まります。
●粗悪品
内部の電解液に、本来水は入っていませんが、そこに水分などの異物が入ることでガスが発生し、膨張して燃えてしまうこともあるそうです。