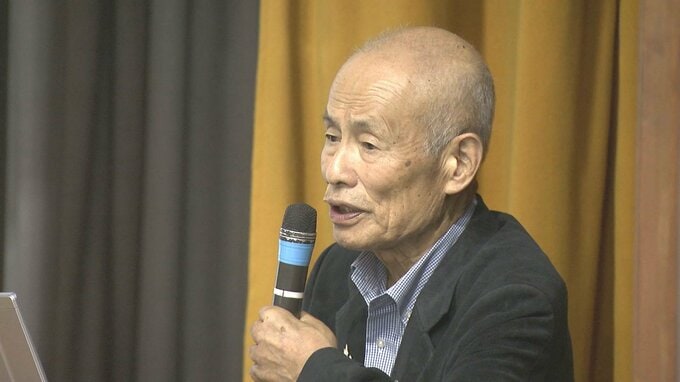2025年10月、山口県山陽小野田市の中学校で行われた平和学習で、壇上に立った1人の男性がいました。日本被団協代表委員の箕牧智之さん、83歳。心不全の悪化で入院中でしたが、外出許可を取り、病院から講演に駆けつけました。
箕牧智之さん
「本当は元気な姿を皆さんに見せたいんですが、さすがに83歳ともなりますと、体が弱って今、実は入院中なんですよ。病院から駆けつけて来たんですよね」
箕牧さんの声は時折かすれながらも、中高生たちに確実に届いていました。座りながらの講演となりましたが、その言葉の重みは変わりません。昨年10月11日に日本被団協のノーベル平和賞の受賞が決定してから1年。世界が注目した組織の代表委員は、今も最前線で平和を訴え続けています。
3歳で体験した原爆の記憶
箕牧さんが語り始めたのは、1945年8月6日の記憶でした。当時3歳だった箕牧さんは、東京から父親の出身地である広島に疎開していました。午前8時15分、広島に原爆が投下された瞬間を、幼い目で見ていました。
箕牧さん
「私は家の前で遊んどったんですけどね、ピカーっと光ったんで、雷ぐらいしか思わなかったんですよね、子どもですから」
父親は国鉄で蒸気機関車の整備の仕事をしていました。原爆投下の日、父親は帰ってきませんでした。箕牧さんが泣きながら家に帰る途中、空から「変なもの」が…。よく見るとそれは紙切れのようなものでした。原爆による放射性降下物は広範囲に降り注ぎましたが、当時は誰も分かりませんでした。
翌日、箕牧さんは「広島がおおごとになっている」と言う近所の人に誘われ、母親と弟とともに、トラックで広島市内に入りました。父親を探しましたが、見つけることはできませんでした。「その間私たちがどれだけの放射能を浴びたことか。放射能ということをみんな知りませんからね。匂いもないし、何にもないから」と振り返ります。父は奇跡的に無事で、原爆投下から数日後、自ら自宅に戻ってきました。
戦後の貧困と母の愛情
戦後、箕牧さん一家は極度の貧困に見舞われました。父は土木作業、母は近所の農家の手伝い。洋服を買う余裕はなく、母親が手作りした胸当て付きズボンやセーター、ボタンが取れかけた服を着ていました。
食べ物が不足する中、母親から「ご飯粒が1粒でも落ちとったら拾って食べなさい」と教えられて育ちました。
箕牧さんは小学生の頃から家事を手伝い、子守りもしました。まきで火を起こし、見よう見まねでジャガイモやタマネギを切っておかずを作りました。「おいしい、おいしい」と言って両親が食べてくれた記憶は今も鮮明に残っています。
小学校5年生の12月、箕牧さんは原因不明の病気で生死をさまよいました。毎日続く高熱。冷蔵庫もない時代、氷で頭を冷やすこともできず、川の水で冷やす程度しかできませんでした。「この子はもう亡くなるかもしれない」。医師から告げられた母は、アメリカから輸入された高価な薬「ストレプトマイシン」を使うことを決意。箕牧さんは一命を取り留めました。
定時制高校から旋盤工に
定時制高校に進学した箕牧さんは、働きながら学びました。月曜から木曜は学校、金土日は農作業。稲刈りや牛の世話など、さまざまな仕事をこなしました。
箕牧さん
「そのお金で散髪へ行ったり、靴を買ったり、授業料を払ったりしたものです」
1961(昭和36)年に高校を卒業し、旋盤工として鋳物工場に就職。初めて受け取った給料の感動を今も覚えています。
箕牧さん
「初めてもらった給料のありがたかったこと。1か月働いて、朝8時から5時まで。会社がお金くれるんですよね。そういうのがまだ不思議だったですよ」
初回のボーナスで母親に電気洗濯機を買ってあげた思い出は、箕牧さんの宝物です。
世界に届いた被爆者の声
2010年、箕牧さんは広島、長崎の被爆者とニューヨークを訪れ、マンハッタンでデモ行進をして平和を訴えました。
箕牧さん
「私のような貧しい人間が飛行機に乗ってニューヨークの方へ行くなんて夢の夢でした」
ニューヨークの教会での講演で、箕牧さんが話した一つのエピソードは、アメリカの子どもたちに深い印象を残しました。原爆で親を失った子どもが、アメリカ人の女性からパンをもらった時、お腹が空いているにもかかわらず、そのパンをカバンにしまったという話です。「家へ帰ったら妹が待ってるから、妹と2人で食べる」。この話を聞いたニューヨークの子どもたちは涙を流しました。
核兵器禁止条約の制定に向けた署名活動にも尽力し、2017年には296万3889筆の署名を国連に届けました。
2017年7月7日、122カ国の賛成で核兵器禁止条約が採択されました。しかし日本は参加していません。
ノーベル平和賞という重責
2024年10月11日、日本被団協のノーベル平和賞受賞が発表されました。「核のタブー」確立への貢献が評価された歴史的瞬間でした。箕牧さんの生活は一気に慌ただしくなりました。県内外から被爆証言の依頼が相次ぎ、8月にはイタリアでも核兵器廃絶を訴えました。
高齢化で直面する組織存続の危機
日本被団協は今、高齢化と後継者不足という深刻な課題に直面しています。全国の被爆者の平均年齢は86.1歳に達し、被爆者数も初めて10万人を下回り、約9万9000人となりました。ピーク時の約4分の1に減少しています。
広島県内の被爆者団体は、1986年の73団体から現在は28団体に減少。会員数も3万3000人から3200人と10分の1に減りました。43%にあたる12団体では、被爆者ではない「被爆2世」が会長を引き継いで組織を存続させている状況です。
それでも続ける平和への訴え
入退院を繰り返しながらも、箕牧さんは被爆体験を継承する活動を続けています。講演の最後に、箕牧さんは将来を担う中高生に最も重要なメッセージを伝えました。
箕牧さん
「平和というのは油断しとったらすぐにね、戦争に流れるということがありますから。皆さんが30代40代、働き盛りの頃に、日本は戦争するかもわからんよ。今の様子を見とったらね。その時には戦争反対ということを、はっきりと言うんよ」
そして教師たちにも訴えました。
箕牧さん
「このかわいい生徒たちが戦場へ行くことがないような教育をお願いをいたします」
被爆者任せではない平和の実現へ
戦後80年ー。戦争の記憶が風化していく中、被爆者が命を削っ て伝え続ける証言を、私たちはどのように受け止め、次世代につないでいくべきなのか。83歳の箕牧さんが病院から駆けつけて伝えたメッセージは、私たち一人一人への問いかけでもあります。