今年のノーベル賞の発表が日本時間の10月6日から始まっていますが、京都大学は今、“ノーベル賞の卵”の育成に力を入れています。
京都大学は今年、将来ノーベル賞級の活躍が期待される50歳未満の若手研究者を表彰する国際的学術賞、「レクチャーシップアワード」を創設しました。栄えある第一回の受賞者は。アメリカの細胞生物学者・ブラングウィン博士でした。
ブラングウィン博士は、水と油のように濃度が異なる水溶液が混ざらずに分離する仕組みが、人の細胞内で起きていることを発見。難病のパーキンソン病やALSなどの根本原因の一つと考えられており、治療薬の開発にもつながっています。
京都大学はこれまで、アジア圏で最も多いノーベル賞の受賞者を輩出しています。しかし、国立大学の運営の基盤となる「交付金」が減り、研究の質の低下が危惧されるなか、京都大学は独自に若手の研究者を育成しようと2009年に「白眉プロジェクト」を開始しました。
(京都大学・白眉センター 高倉喜信センター長)「国際公募で優れた人“白眉”を見つけようと、中国の故事に由来する、優れた者の中の一番優れたもの。“ノーベル賞受賞者の卵”といっても過言ではない」
白眉センターにはいま17倍以上の倍率のなかから選ばれた20~40代の国内外の若手研究者、66人が在籍しています。
(京都大学・白眉センター 松本徹特定助教)「宇宙の砂の研究をしていて、地球の材料となった水や生き物の材料がどうやって地球に運ばれてきたかとか、生命の起源について学問が深まればいいかなと」
与えられる時間は5年間。研究者たちには給料だけでなく、研究室や研究費が提供されますが、研究の成果を求められることはありません。
(京都大学・白眉センター 高倉喜信センター長)「給料と研究費を毎年数億円これに投資している。日本の他の大学や世界に羽ばたいて、京大が優れた白眉研究者を輩出したというのが大事なんだと」
去年4月から、白眉センターに所属する高木佐保さん(34)は、今年4月に出産したばかりですが、白眉センターの研究者は研究以外の仕事が免除されるのが大きな特徴です。
(京都大学・白眉センター 高木佐保特定助教)「研究に専念できるというところが一番魅力的で、大学の先生は研究以外のこともいろいろやらないといけないんですけども、本当にこういう制度があるおかげで研究が続けられている」
高木さんの研究テーマは「ネコの家畜化」。ネコは元々、繁殖期と子育て期以外は単独で行動しますが、アメリカと日本で飼われているネコを比較すると、アメリカのネコは日本のネコよりも人懐っこい性質が見られたといいます。
自宅でも2匹のネコを飼っている高木さんに実験の様子を見せてもらうと…
(京都大学・白眉センター 高木佐保特定助教)「ネコが思い出を持っているのかというのを調べる実験」
4枚の皿のうち、2枚にはエサを、1枚には何も入れず、もう1枚にはただの小石を入れます。そして、1枚のエサは食べさせ、もう1枚のエサは食べさせません。約15分間、別の部屋で遊ばせたあと、皿の中身を全て無くした状態でどの皿を選ぶかを観察します。
すると、約4割のネコが「エサを食べることができなかった」という記憶を元に、その皿を最初に選ぶという結果に。これはネコが「食べられなかった」という「嫌な記憶」を思い出した結果、その皿を選んだということが言えるそうです。
(京都大学・白眉センター 高木佐保特定助教)「ネコが前の経験を思い出して、先ほど食べられなかったからここに向かうという解釈ができる。(ネコが)一度きりの記憶を取り出す、思い出のような記憶がある」
ネコにも思い出があり、その記憶を元に行動する過程を調べることが動物の「家畜化」や、ひいては人間社会の成り立ちに関わっていると話します。
(京都大学・白眉センター 高木佐保特定助教)「集団の中で協力社会を作るために、怒りっぽい人を排除する力が人間の世界で働いたのではといわれている、自分自身で自分を家畜化していくということで、どんな認知能力を得られたのか、どんなコミュニケーションができるのか明らかになる」
“研究の種”を見つけ、日々まい進する「ノーベル賞の卵」たち。彼らが栄光を手にする日も近いのかもしれません。
注目の記事
外免切替が厳格化「問題が難しくなった」外国人から戸惑いの声も 住民票の提出義務化、試験内容も大幅見直し

和式トイレの水洗レバー「手で押す」?「足で踏む」? 街頭取材では拮抗…それぞれの主張は 正しいのはどっち?メーカーに聞いてみると…

【台風情報】新たな台風23号発生「台風のたまご=熱帯低気圧」発達 沖縄・奄美から本州に影響か 3連休にも【雨と風のシミュレーション8日(水)~13日(月祝)】台風22号・23号気象庁進路予想 台風情報2025

コーヒー豆を運ぶトラックで「息子は天国に行った」夢を絶たれた29歳のバリスタ 遺志を継いだのは母だった 【人をつなぐコーヒー・前編】

“セクハラ” に揺れる南城市 市議会解散は古謝市長の正当な権限か、乱用か…市議選に2000万円超は税金の無駄? 専門家が語る「制度の想定外」
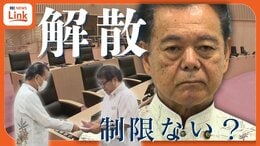
「いまでも5日は苦手」事件と向き合い続けた父親 娘のストラップはいまも… 20年以上続けたブログにも幕を下ろし 廿日市女子高生殺人事件から21年

「逆にお聞きしますが、僕がパクられた時に京アニは何か感じたんでしょうか」言い返す青葉被告を裁判長が制止した 遺族がはじめて被告人質問に立つ【ドキュメント京アニ裁判⑪】

「投資用物件とフラット35」で相次ぐトラブル…住宅ローン4000万円『一括返済』求められ「絶望」勧めた不動産会社Xに取材を申し込むと

幼少期に性被害「ずっと自分を殺したかった」加害繰り返した男性「反抗しない子どもに…」当事者たちの証言【MBSドキュメンタリー映像‘23】

「お金ないし誰の子どもかわからない」路上で赤ちゃん出産…傍聴から見えた女の半生「風俗店勤務でホテル転々…給料の大半はホスト通いに」「過去12回の出産」「妊娠を相談する人がいなかった」





