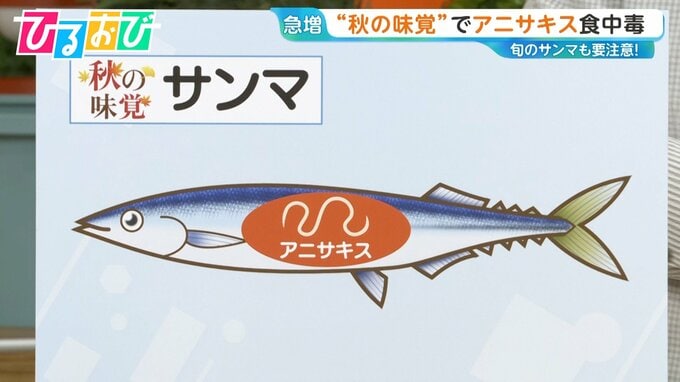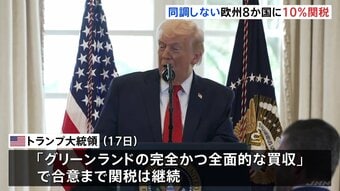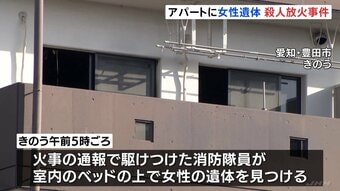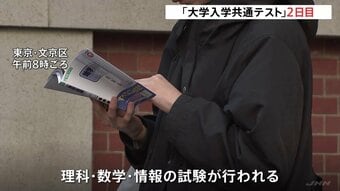サンマやイカなど、海の幸が一段と美味しい季節になってきました。
ただアニサキスによる食中毒にも注意が必要です。
食中毒の発生件数1位は「アニサキス」
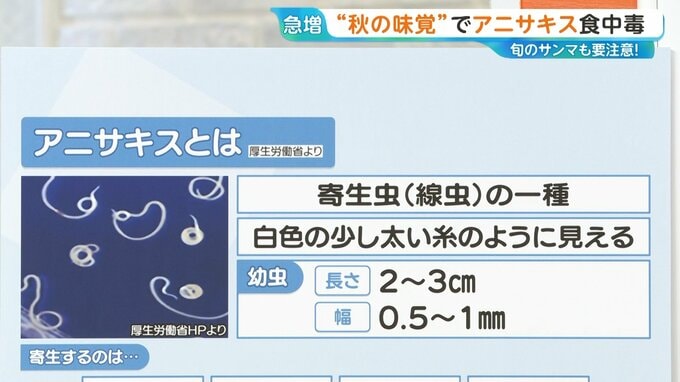
アニサキスは寄生虫(線虫)の一種です。
幼虫は長さが2~3cm、幅が0.5mm~1mmで、白色の少し太い糸のように見えます。
寄生するのは、
・サンマ
・カツオ
・サケ
・サバ
・マグロ
・アジ
・イワシ
・ヒラメ
・イカ
などの魚介類です。
アニサキスによる食中毒の症状は、生の魚介類を食べた後、1時間から数日で出現します。