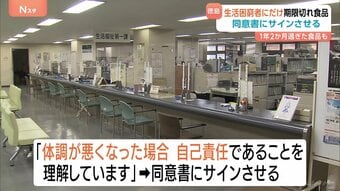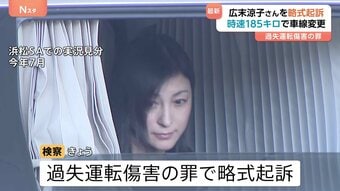「あっ、まいばすけっとだ」と思ったら、その100m先にもまた「まいばすけっと」がある——。イオン傘下の小型スーパー「まいばすけっと」は、首都圏で急速に出店を続け、2025年7月末には1250店舗に達しました。2010年にわずか100店舗だったことを考えると、15年で12.5倍という驚異的な成長ぶりです。
最近、SNS上で「まいばすけっとは都民への罰だと思ってる」というポストが3880万ものインプレッションを獲得してバズりました。「品揃えがつまらない」というイメージがある一方で、多くの人が日常的に利用している不思議な存在。そんな「まいばすけっと」の急成長の裏には、独特の経営戦略があります。
店舗拡大の秘密はどこにあるのか
「まいばすけっと」は2005年に横浜市で実験的な1号店を開店して以来、毎年およそ100店舗ずつ、4日に1店舗のペースで増え続けています。現在は東京、千葉、埼玉、神奈川の1都3県で約1200店を展開していますが、その特徴は「どの店舗も同じレイアウト、同じ品揃え」という点。まさに「細胞分裂を続けるアメーバ」のような印象を与えます。
そもそも「まいばすけっと」のコンセプトは「コンビニサイズのイオン」。大型スーパーが近くにない都市部に住む人たちの「日常生活の食のインフラ」として機能することを目指しています。「トップバリュ」というプライベートブランドを活かし、コンビニよりも1割から4割ほど商品が安いという価格設定や品ぞろえの豊富さも、日常使いに適した特徴です。
繁盛店をつくらないという逆転の発想
「まいばすけっと」の無限増殖には、実は「繁盛店をつくらない」という意外な戦略があります。100m先に別の店舗があれば、客足は分散します。これにより常に一定の来店客数を保ち、オペレーションを効率化しているのです。
セールや特売がないことも特徴です。「エブリデーロープライス(EDLP)」という、毎日比較的安い価格で販売する戦略を採用しており、日によって客数が大きく変動しません。これにより、2~3人の最小限のスタッフで店舗運営が可能になっているのです。
さらに「まいばすけっと」は、コンビニのような店内調理や公共料金支払いなどのサービスを省略。社内スポットワークのような仕組みで、スタッフはアプリでシフトを確認し、近くの店で2時間から働けるようになっています。