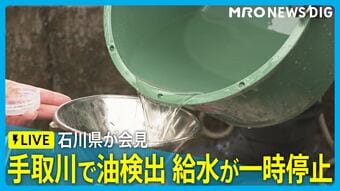石川県輪島市に住む100歳の女性が語る戦争の記憶です。戦時中の暮らしは、そして、奥能登で経験した進駐軍との意外な交流とは。100年の人生を取材しました。
桶本くにゑさん「相手にならん。アメリカを相手に勝つわけがねぇげんて」
当時の率直な気持ちを語る桶本くにゑさん、100歳。輪島市で娘の靖子さんと2人で暮らしています。

輪島で9人きょうだいの3番目に生まれたくにゑさんは、当時、地元の尋常高等小学校に通っていました。繰り返し習っていたのが、明治天皇が発布した道徳や教育の基本理念である「教育勅語」です。
くにゑさん「『朕惟うに我が皇祖皇宗国をはじむること宏遠に徳を樹つること深厚なり…』これは覚えなならんかった」(教育勅語を暗唱)
靖子さん「子供の時から刷り込まれているから、今の人と感覚が違う」
くにゑさん「日本は『神国』だと信じていた」
くにゑさんが子どものころは輪島からも毎日のように戦地に向かう兵士がいたと話します。
くにゑさん「駅前の通りで1日に1回でも2回でも並ぶ。きょうは遺骨、今日は送ると言って、通りに立って兵士を送ったり迎えたりする。学校の勉強どころではなかった。運動場は全部畑、運動はせずに耕して、カボチャを植えていた。食糧を確保するためにそんな仕事がいっぱいあった」
戦争が激しさを増す中、高等小学校を卒業したくにゑさんは、貴重な若い女性の労働力として働きに出ます。
くにゑさん「富山の不二越に友達と一緒に勤めた。ここは寮があって泊まれた。そこで飛行機のプロペラの真ん中の丸い部分を掘る仕事を与えられた。親代々手先が器用で、細かい仕事ができた。この位の大きさだった」
記者「その作業してる時はどんな気持ちだった?」
くにゑさん「何で戦争を始めるのかと思った。勝てるはずがない」
太平洋戦争が始まったころ、現在の石川県かほく市にあった親戚の家に身を寄せます。
くにゑさん(歌)「常に非常時世の中は、力を合わせて働けや働けや♪」
当時、流行っていたという歌。
くにゑさんは、親戚の家から金沢市大和町の工場に通い、パラシュートのひもを作る作業に従事します。
くにゑさん「とにかく働け働けと言うことで働きに行った。そこから金沢の落下傘のひもを練る工場に行った。細いのを練って太くする、そういう仕事」
親戚の家と職場を往復する日々。その中で、くにゑさんに転機が訪れます。
くにゑさん「戦争が始まって、男の人が兵隊に行って、先生が足りなくなった。試験を受けたら運よく受かった。私は高等小学校しか出てないし、女学校や中学校を出た人もいるが教員になれた」
ふるさとの輪島で就いた教師の仕事。
激しさを増していった戦争にくにゑさんが感じていたこと。
くにゑさん「若い人が自分の希望を叶えられず死んでしまうのが一番情けない。ただの人ではない、みんな夢のある何かになろうという人達ばっかり戦争から帰って来られない。終戦によって若者の命が救われるのが一番。戦争に行かなくてもよくなったということが」
1945年、終戦。アメリカからの進駐軍は、くにゑさんの働いていた学校にも。
くにゑさん「進駐軍がそのまま土足でドカドカと学校に上がって来た。引き出しなどを開けて中を見て、廊下を一回りして帰っていった。びっくりした、でっかい身体に大きい靴を履いてダッダッダッと入ってきた」
戦後、輪島崎町の天神山にはアメリカ軍のレーダー施設があり、くにゑさんの夫は、そこで警備の仕事をしていました。
これは1955年頃、地元住民と進駐軍の軍人がパーティをした時の写真です。

アメリカ軍の男性の隣に立っているのがくにゑさんと靖子さん。写真の中には10年前まで戦争をしていたとは思えない多くの笑顔があふれています。
靖子さん「チョコレート、コンビーフ、金属のパッケージに入ったバター。そしてクリスマスプレゼントの長靴に入ったお菓子を貰った記憶がある(と母が言っている)」
このころ、手先の器用さを生かして妹と輪島の朝市で「シスター洋装店」というオーダーメイドの洋服店を始めていたくにゑさん。

松ぼっくりと布を組み合わせた飾りに、人形用の着物。手織りの布をあしらったストラップ。今も趣味の手芸を続けています。

くにゑさん「全部自分で考えて作っている」
くにゑさん「100歳になって3カ月も4か月も経った」
靖「好きな事出来て良かったね」
くにゑさん「まだまだしたいことはある」
戦争が終わって2025年で80年。今、くにゑさんは、「自分のやりたいことができる」そんな世界に生きています。