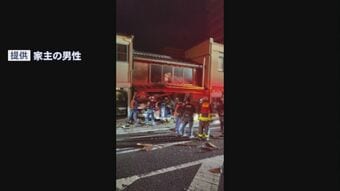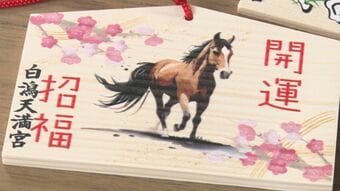太平洋戦争が始まると燃料不足が日に日に深刻になり「ガソリンの一滴は血の一滴」と代用燃料が懸命に作られました。
島根県西部の邑南町ではそのために使われた鉄の窯が寺の釣鐘として再利用され終戦から80年経った今も残っています。
中国山地の中にある島根県邑南町の西隆寺です。
町指定文化財の大日如来像を祀る古刹ですが、寸胴で模様もない奇妙な形の釣鐘が吊るされています。
邑南郷土史研究会・中山光夫代表
「日本は燃料がなくなったという時に松の根を掘って。そしてそれを集めて、で蒸し焼きにして。ガソリンのようなものが出るんですね。それを精製して取った窯です」
地元の邑南郷土史研究会の代表、中山光夫さんです。
邑南郷土史研究会・中山光夫代表
「(鐘が金属)供出によってなくなっていた。で、終戦の時に河原に転がっていた松根油のドラム缶(窯)が7、8つあったと思うんです。その1つを持って帰って吊り下げた」
太平洋戦争中、不足するガソリンを少しでも補おうと、国は松の根を蒸し焼きにして作る「松根油(しょうこんゆ)」製造を各地に命じました。
これは戦後の米軍撮影の映像ですが、松の根を細かく割って蒸し焼きにすると濁った液体が出て来ます。
その上澄みをすくい取り精製するとガソリンの代わりに使える松根油になったということです。
釣鐘として残る窯の内側には、タールのようなものが沢山こびりついていますが、これも80年前のものなのかも知れません。
ほかにも代用燃料にしようとⅤ字形の傷を付けて松脂を採った松の木が各地に残っていますが、戦争のため必死で燃料を調達しようとしていたことが窺えます。
邑南郷土史研究会・中山光夫代表
「大正時代から町筋だったんですね。それで、ここが(松根油製造)工場なんかをやるほどの周囲の人口やら飲み食いする所もあったということです」
邑南町内では3か所に工場が造られ住民総出で松の根を掘り増産に協力したということで、当時の海軍大臣による表彰状が残っています。
そして戦後、不要になって転がっていた窯を金属供出でなくなっていた鐘の代わりに吊るしたようです。
もともと釣鐘ではない上、鉄なので普通の銅の釣鐘より鈍い音がします。
邑南郷土史研究会・中山光夫代表
「門徒さんがいないから(鐘が作り直されず)これがずうっと吊り下げられていた」
中山さんは、戦後しばらくの間は釣鐘として再利用された窯がほかにも各地にあったはずだが、西隆寺は半世紀余り前に住職がいない寺になったこともあり、釣鐘を作り直す話は起こらず、松根油の窯がそのまま残ったのだろうといいます。
現在も残っている窯は、全国でも4か所ほど。
その神社に残る窯も西隆寺と同じ大きさと形に見え、松根油の大量生産を目指して一定の規格で窯を量産した可能性もありそうです。
しかし膨大な労力を傾けて増産された松根油が大きな戦力になったという記録は残っていません。
中山さんは案内看板を作ったり、見学会を開いたりしていて、時代の流れの中で先祖たちがたどった歴史を伝えていきたいといいます。
邑南郷土史研究会・中山光夫代表
「先人として頑張ってもらったんだよ。知っとって無駄にせんようにしようねと(伝えたい)」
戦後80年の夏、激動の時代を知る鈍い鐘の音が山あいの町に響きます。