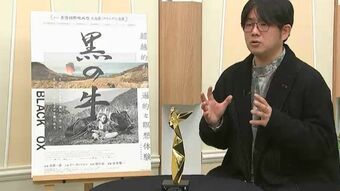日本で広がる“ファースト”の波
政治から社会、生活においてまで、英語の“ファースト”が日本人に浸透しています。受け入れられるようになった理由はどんなことが考えられますか?
進藤貴子教授(川崎医療福祉大学医療福祉学部 臨床心理学科)
「どんな人も人として尊重される、一人一人の国民の暮らしを大切にする、という人権意識の広がりとともに“ファースト”は馴染んできていると思います」
「一方で、日本人の共同体への心が少しずつ変わってきていると思います。共同体のために個が犠牲になる世界の国々が“自国第一主義“のナショナリズムを出しているなか、『うかうかしていると権利を侵害される、という不安をいだいた日本人に響くフレーズ』だったと思います」
大切なのは“心のファースト”
発達心理学【画像④】の視点で見ると、まず“自分が大切にしてもらうこと“が前提にあり、そこから、他者への思いやりとつながっていくことが、バランスのとれた心の育ちの順序と進藤教授は言います。
自分の“心”を大切にされることを基盤として、周りの人を幸せにする。周りの人たちが幸せになり、自分がより幸せになる、というサイクルが、「自分ファースト」の望ましい形だということです。
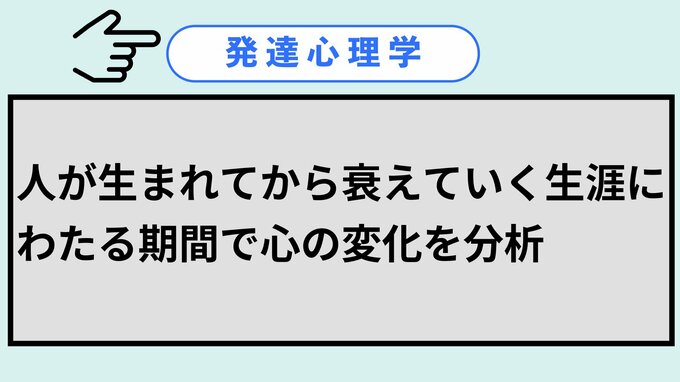
進藤貴子教授(川崎医療福祉大学医療福祉学部 臨床心理学科)
「一枚のパイを皆で分け合うとき、自分が優先的に欲しいだけ取り、他の人は損をしても構わないという他者排除の考え方は、不信と孤立につながり、結局、満たされなさが残りますよね。逆に自分を置き去りにして、他人のためだけを考えるのも、不健全な状態をもたらします」