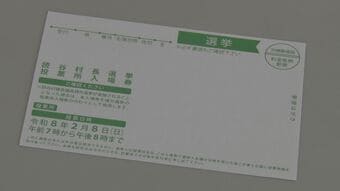「水滴」で受賞した芥川賞など、作家として数々の賞を受賞し功績をあげてきた目取真俊さんですが、15年以上も長編小説を発表していません。背景には普天間基地の辺野古への移設に反対する活動などに連日参加するようになったことがありました。
「“戦後”80年を迎えた沖縄」「米政府が考えていること」「祖父母から学んだこと」「今後の小説の構想」など、多岐にわたるテーマについて目取真さんに聞きました。

【80年前の教訓】
――今の辺野古の状況を見て思うことは?
「辺野古の工事の様子を見れば、日本がこの30年間衰退する理由がよくわかりますよ。最終的に1兆円を超える工事費用の規模になるのかもしれません。本来は教育や産業振興、研究開発とかにかけるべきお金を使っているわけですから、こんな国は絶対発展しないですよ。政府の皆さんは優秀なんですよ。日本が太平洋戦争に突入しますよね。どう見ても勝ち目がないということは分かっていたんです。あの当時の人たちも優秀な人はたくさんいた。当時の海軍大学校を出た、東大工学部を出た、こんな優秀な皆さんがそれでもやってしまう。人間というのは一旦視野が狭まって一つの道が敷かれたら、そこから外れて別の角度から検討することができなくなってしまう。優秀だから正しい選択ができるとは限らない。それが80年前の教訓ですよね」
【米政府は冷静に分析】
――基地移設工事が急速に進んでいる?
「基地の問題は1995年の9月4日に米兵が少女を強姦した。そこから始まっている。その直後に沖縄で大きな反対運動が起こって、県民大会も開かれて、おそらく米国は慌てたはずなんですよ。もしかしたら全基地撤去みたいな、コザ暴動みたいな事態が起こるんじゃないかと。だから彼らはそれを何とか抑え込むために、普天間基地の返還を持ち出したわけですよね。だけど米国は沖縄のことを観察して分析して現状を見たときに、そこまではいかないと見切ったんだと思います。もはや日本という国、あるいは沖縄という地域で、暴動というような形で大きなことは起こらないと。例えばフィリピンの米軍基地だったら、米兵は夜中に1人で酒飲みに行けないですよ。夜中に酒を飲みに行っていきなり後ろから刺されることもないわけですよ。日本は特殊な国だと思います。80年経ってもまだ米軍は軍隊を置いて、新しい基地を作ろうとしているんですから」
【抗議活動をするは変わった人】
――抗議活動を続ける理由は?
「今の時代はコスパが悪いかとかすぐに成果がでないとやらない。それでいいんですかという話ですよ。最初から勝てる勝負だったら誰だってやりますよ。でもやっぱり誰かが抗議の意思を示さなければ、100パーセント認めたことになるわけですよ。そういった損な役回りの人間がいるわけですよ。例えばシマウマがいて、他のシマウマを助けるためにライオンに食われるやつがいるわけですよ。それは、そのシマウマが愚かだから食われるわけじゃないわけですよ。年をとって衰弱して自分が死ぬ代わりに子供たちを生かすとか、集団の中には必ずそういった人たちがいるわけです。もうこの歳になったら自分たちは損な役回りのために生まれてきたような人間だと思っています。こういうことをやる人は、今の社会ではどこか変わった人なんですよ」

【本当の連帯感】
――変わった人とは?
「何かの理由があったんですよ、こういうことをせざるを得ないような。理由は1人1人全部違うと思いますよ。やる人は1人で来ます、単独者ですよ。でも実際に抗議活動を支えているのは、そういう人たちなわけです。地道に黙々とやっている皆さんなわけですよね。年配の皆さんはSNSで発信することもないから知られることもないわけですよ。取材する人もいなければ。ルポルタージュで取り上げる人もいない。だから結局人を支えるのは、近くにいて、地道に頑張っている人がいると。その人たちを置き去りというか見捨てて、自分1人だけやめることはできないという心情です。でもそれが本当の連帯感だと思います」
【話を聞いてくれることが嬉しかった】
――好奇心が強い子どもだった?
「自分の周りには、ちゃんと話を聞いてくれるおばあちゃんがいたわけですよ。年寄りだから子どもが訪ねたら、なんでもかんでも聞いてくれるわけですよね、一生懸命。それはやっぱり孫にとって、とても嬉しいことですよ。だから新しい知識を得て、おばぁに教えてあげようという気持ちになるわけですよね。それが本を読むきっかけにもなっていくわけです。何か調べるクセというのは子供の頃に作られたもんですよね」
――祖母は良き話相手だった?
「自分の祖母はとても関心の強い人で、自分が子供の時代はアポロが月に行った時代なんですよ。ずっとテレビを見ているわけですよ。祖母が晩年になって、85歳の頃に残したノートがあった。ノートの切れ端を見たら、当時、小惑星がどこかに行く、ハヤブサかなにかの記事を全部新聞から書き写しているんですよね。これを見たときに、ずっと宇宙に関心を持っていたんだなと思って、おそらく理解はしていないですよ。だけどノートに新聞の記事を一言一句書いているわけですよ。この姿勢は、おそらく無意識のうちに自分の中に影響を与えていますよ」
【東京は別世界】
――2023年に韓国の国際文学賞「第7回 李浩哲(イ・ホチョル)統一路文学賞」を受賞しましたね。
「最近、韓国で沖縄文学が注目されているのは、研究者がいて熱心に翻訳してくれているわけですよ。翻訳が出るから、読者も生まれてくるわけですよね。彼らが沖縄に関心をもつのは、大和とは違うからですよ。沖縄は戦後27年間の米軍統治があって、米軍基地が集中していると。韓国も米軍基地があるわけですよね。韓国でも反米運動が起こったり、反基地運動が起こったり、そういう現場があるわけですよね。だから辺野古の問題にも関心を持って沖縄まで来る人もいる。沖縄の小説を読んでも、リアリティを感じるんだと思います。僕からすれば、心理的な距離はずっと東京の方が遠いですよ。東京に行ったら、もう別世界ですよ。全く違う世界だなと。この人たちに沖縄の基地問題を考えることできるんだろうかというように思います。この空間の中で忙しく動いている人たちの中で、それはやっぱり作られたものですよね。意図的に東京周辺から基地を全部排除していったわけですから。そういった中で沖縄の文学を読ませるというのは難しいんですよ。最初からもうリアリティの基本が違うわけだから」
【すべての作家の願望】
――今後の小説の構想は?
「たくさんあります。鳥の卵のように、生まれてこなくても卵がお腹の中にたくさんあるわけですよ。それを1個1個殻に包んで、排卵する作業が作品を作るということなんですけどね。ただ、人生の残り時間は限られている。日々の活動をする中で、書ける時間も本を読む時間も限られている。それをどうコントロールして、どこに比重を置いていくか。まだ沖縄戦について、いくつか書かないといけないものがあるし、あるいは沖縄の戦後の中で自分が見てきたことや体験してきたことについて少なくとも書いておかなきゃいけないと感じています」
――15年以上、長編作品を発表していないことについては?
「作品が長いかどうかというよりも、本当にこの作品を読んだ後に強く心に響いて忘れがたいなと、20年たっても30年たってもまだ人々に読み継がれて、感動する人がいるかとかですね、それこそが一番大事なことなわけですよ。漱石にしろドストエフスキーにしろ、100年たっても200年たってもやっぱり読めるのは、そういった要素があるからなんです。全ての作家にとって一番の願望がそれだと思いますよ。ただそれは努力してもなかなか達成できないわけですよ。だけど達成できないからといって諦めて何もしなければ、最初からゼロですからね。仮にやって駄目だったとしても、やっぱりやり続けるしかないわけですよね」