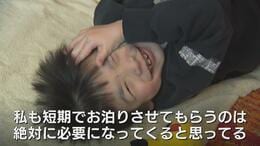阪神・淡路大震災から30年。被災地では犠牲者を悼む追悼行事が行われ、鎮魂の祈りに包まれました。当時、震災発生後にボランティアとして現地入りし、避難所の運営などに携わった男性を取材しました。
大分市にある県防災活動支援センターの清松幸生さんは、震災発生から3週間後に現地入り。そこで目にしたのは避難所生活の難しさでした。

清松さん:
「高齢者が体育館の隅で過ごしていたので待遇を改善しないと災害関連死が出てしまうという思いがあった」
現地での活動を通して、地域住民が防災の知識やスキルを持つ必要性を痛感した清松さんは「防災士」の養成に乗り出します。
養成講座への参加者は広がりを見せ、大分県は人口あたりの防災士の数が全国2番目に多くなっています。
清松さん:
「警察や自衛隊のような機能集団ではなく、地域の中で普段のコミュニティの活動をしている地域集団の中に防災士がいることの良さを認識してもらえるといい」
一方で、防災士は災害時に住民を守ってくれる存在ではなく、自らの命は自らで守ることが基本だと強調します。

清松さん:
「自分の命は自分で守る。そのために備蓄はこうしないといけないとか家具の固定もしなくてはならないし、ひとり一人が自分で考えるということが必要です」