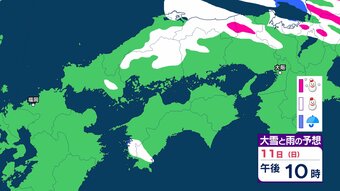12月19日、国の補助金が削減され、ガソリン代が値上がりすることになりました。
この値上げを受け、12月25日の経済産業省「石油製品価格調査の結果」のレギュラーガソリンの店頭小売価格調査の結果では、全国47都道府県全てで値上がりし、全国平均では1リットルあたり180.6円、最も価格が高かった長野県では190.8円、次いで高知県188.9円、山形県186.6円となりました。
さらに、来年1月にも5円程度の値上げが予定されていますが、この記事では経済産業省の事業内容を踏まえ、値上げの理由をわかりやすくお伝えします。
なぜ5円値上げ?その理由をわかりやすく!
まず、12月19日の値上げは経済産業省の「
そもそもこの激変緩和事業とは、
2022年1月に緊急措置として開始し、今もなお続いているこの激
具体的には、基準価格168円から「17円分」についての補助率を、月10分の3ずつ見直
政府は「国民生活の急激な影響を緩和するため、