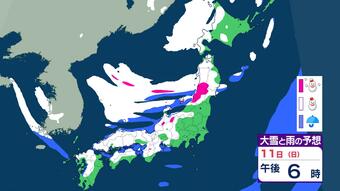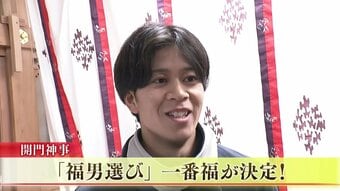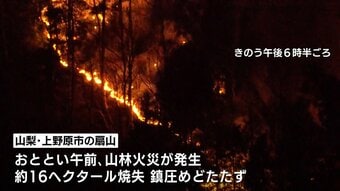■専門家の意見はー

日本医科大学特任教授 北村義浩氏:
このデータは非常に貴重だと思いますので、今後しっかり検証した方がいいと思います。
ただ、感染症の先生方のお立場からちょっと擁護すると、「テーブルチェック」は、しっかりした予約システムで、しっかりした感染対策を行うレストランが中心。予約を入れるお客さんも、感染対策をきちんととるようなタイプで、少人数だったり、お酒も過度に飲まないような取り組みをしている可能性もあります。
また、昼・夜どちらのお客さんの流れをグラフにしたのか、あるいはお酒が入っていたのかなどの細かいところまではなかなか把握できないと思うので、そういう細かいデータも入れて、いずれはしっかりチェックしなければいけないと思います。
今回の第7波では家庭内での感染が最も多く、飲食店での感染は非常に少なかった。ただやはり家庭に持ち込まれたその元々の原因の感染源はどこだったのかは今でも不明なんです。
感染者数が上がるときは、お盆や祝日だったり、一部のお祭りなどが感染の直前に行われていることもわかっていますので、やはり人流というのは完全に否定できるものではない。非常に難しいところですね。
恵俊彰:
データを見ると、来客人数と感染者数は必ずしも比例してるわけじゃないということですよね。
落語家 立川志らく:
飲食店をあまり攻撃するのは気の毒だってのが一つある。ただ北村先生がおっしゃる通り、感染対策をあまりしていないお店のデータも取ってみるべきだと思う。
また専門家の中には、人流はそれほど関係なく、感染症ってのはとにかく天井まで上がれば必ず落ちるんだっておっしゃってる方もいるんで、いろんなデータを見ることが必要ですよね。
弁護士 八代英輝:
気になったのは、飲食店と呼ばれるジャンルの幅が大きすぎる。
例えばカラオケスナックのように歌うところも飲食店で、立ち食いそばのように、ほぼ隣の方と喋らないような営業形態のところも飲食店。
飲食店というような大きなジャンルではなく、感染リスクの高い営業スタイルということで、細分化した方がいい時期なんじゃないかと感じますね。
(ひるおび 2022年9月22日放送より)