「土居分小菜(どいぶんこな)」という野菜をご存知でしょうか?

岡山県北の真庭市の一部の地域でしか栽培されていないため“幻の伝統野菜”とも呼ばれています。

実は地域のイメージキャラクターの兜の部分に使われているのも土居分小菜です。
江戸時代から栽培 消えかけた“幻の野菜”の歴史とは
この野菜、ある理由で一度は消滅しかけたんですが、地域をあげて復活させようという輪が、いま広がりつつあるんです。いったいその歴史は。そしてどんな味なのか。一般には流通していない「幻の野菜」に迫りました。

一見、小松菜のような…はたまたほうれん草のような…この青菜が「土居分小菜」です。この地域でしか栽培されていない野菜です。

(二川地域集落 支援員 稲田恵子さん)
「二川地域の土居分地域というところがありまして、そこで昔から作られて、食べられていた野菜で、二川の独自の野菜になるそうです」

真庭市の北部、蒜山高原の南に位置する二川地域。冬の最低気温はマイナス10度になることもあり、多い時には80センチほど雪が積もります。「土居分小菜」はそんな雪の下でも育つのが特徴。江戸時代から栽培されていて、野菜が少ない寒い時期に重宝されてきました。しかし、その存在は一度は消えかかっていたといいます。

(二川地域集落 支援員 稲田恵子さん)
「土居分地域というのが、湯原ダムができるときに、ダムに沈んだという形で地域自体がなくなってしまった」

1955年に完成した湯原ダムです。そのダムの完成に伴い、いくつかの集落がダムの底に。土居分地区もその1つでした。
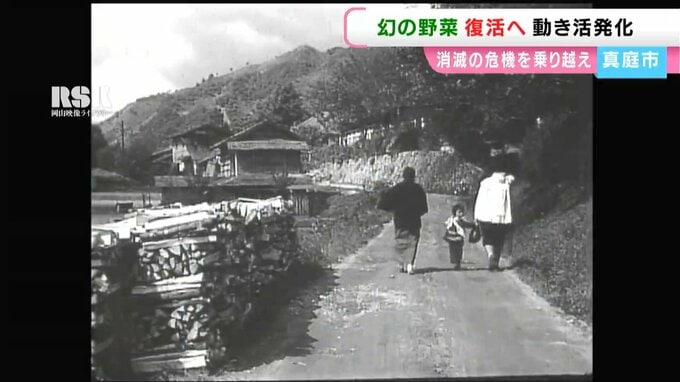
地区とともに土居分小菜は途絶えたものと思われていました。ところが…二川地域の中の別の地区の人たちが種を大切に保管し、それから70年近く栽培を続けてきたといいます。販売はせず、あくまで家庭用でした。その味は?













