■絶滅危惧種のカタツムリ“ヒラコベソマイマイ”の危機とは
なかなか姿を見せてくれないヒラコベソマイマイ。小さな命は、これまで、2度の危機に見舞われた。1度目は、『高知南国道路』の開通だ。2015年、高知南ICから、なんこく南ICまでの区間が、生息地を通ることになったのだ。このため、国土交通省は2010年、現在の場所にヒラコベソマイマイを含む、約120匹のカタツムリの引っ越しを行った。

石灰質の環境を好むことから、引っ越し先は約700メートル離れた、同じ石灰質の場所を選んだが、小さな生き物にとっては大きな変化となる。
▼山崎さん
「“移動”というのは、隠れる場所や他の生物との絡みなど、いろんなことが変化するので、ストレスはかなりかかると思います。」
2つ目の危機は、夏の暑さ。2022年は、6月の降水量が例年の半分以下と少なかったうえに、8月までの3か月間のうち、『57日』が真夏日となった。暑くて雨の少ない夏は、ヒラコベソマイマイにとって「良い状態ではない」という。
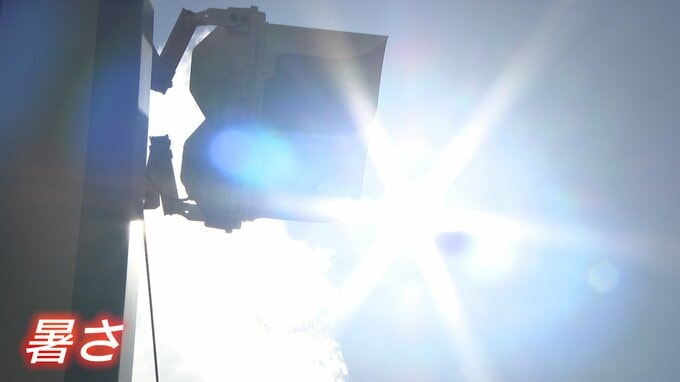
▼山崎さん
「乾燥した環境というのは、陸産貝類(カタツムリ類)にとって、非常に苦手な環境。梅雨が少ないと移動がしにくい。暑すぎてもだめなんですよね、移動はできない。暑すぎる、出会うことも難しくなる、出会わないと子どもができなくなる。あまりいい状態ではないと僕は考えます。」
■生息調査(3回目)ついに…
前回の調査からさらに20日後。調査場所を少し変え、3度目の挑戦だ。調査を始めてから10分後…ついにヒラコベソマイマイが!!

▼山崎さん
「あ!見つかりましたね!ここにいますね。まだ完全な大人ではないように見えるんですけどね。ここで確認したの、生きてるのは初めてなんで非常にうれしいです。ほっとしています。完全に成長しきっていないってことは、ちゃんと子どもが生まれていることなんで、この環境が非常にいいのではないかと僕は思います。」


世界中、どこを探しても南国市の稲生地域にしか生息していないヒラコベソマイマイ。山崎さんは希少な生き物のために私たちができることは「必要以上に干渉をしないこと」という。
▼わんぱーくこうちアニマルランド 山崎博継さん
「干渉しすぎると動物の生活空間に影響を及ぼすので必要以上に干渉せず、できるだけその環境の保全・維持をして行く方が良いのではないかと思います。」

私たちの生活がより便利になる一方で、こうした希少な生き物の暮らしに、大きな影響を与えていることを忘れてはならない。高知県内には、ほかにもツキノワグマやヒメノボタンなど、絶滅危惧種に挙げられている動物や植物が『934種類』いる。高知の豊かな自然を守るために、まずは、こうした生き物を知ることも、大切なことなのではないだろうか。


















