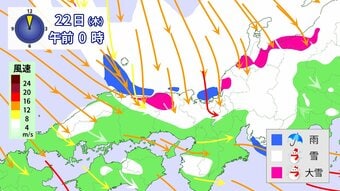広島カキといえば全国一の生産量ですが、昔に比べると、ずいぶん落ちているそうです。原因の一つが、カキのエサとなるプランクトン不足です。広島県は、このプランクトンを増やそうと、昨年度から “ある実証試験” を始めました。舞台は下水処理場です。
広島カキの産地の一つ、広島市中区江波地区です。カキ打ち場では水揚げされたカキが次々にむき身にされています。

シーズンも後半を迎え、身もよく太っていますが、業者は昔に比べ育ちにくくなったとこぼします。
米康水産 米田輝隆 前社長
「昔の半分でしょうね、生産量も、身入りも。けっこう落ちていると思います」
米田輝隆 さんは、県漁連の会長を務めています。その漁協の関係者が問題にしているのが下水処理場から出る水です。
米田輝隆 さん
「 “栄養塩” のない水が毎日毎日、各下水処理場から出てきますので、きれいな水なんでしょうけど、なかなかカキも育ちにくい」

栄養塩とは、カキのエサとなる植物プランクトンの生育に必要な窒素やリンなどです。下水処理場に流れ込む下水には栄養塩がたくさん含まれています。ところが、現在の排水基準で処理すると栄養塩がほとんどなくなります。
そこで、県が昨年度から一部の下水処理場で始めたのが、「能動的管理運転」の実証試験です。基準値を緩和して栄養塩の排出量を増やし、その効果を調べます。
広島県 水産課 木村淳 課長(当時)
「緩和運転することによって、生物がよく育つかどうかを確かめるとともに、やり過ぎたら悪影響が出る。環境に悪影響がないかも同時に調べながら今回、取り組みを始めている」