これまで活発な活動を繰り返してきた桜島の火山活動について振り返ります。
桜島では、1914年1月12日に20世紀国内最大規模の噴火となった「大正噴火」が発生。噴火の後、マグニチュード7.1の地震も発生し、死者は58人にのぼりました。その後も噴火が相次ぎましたが、特に1980年代は南岳山頂火口の活動が活発になり、古里地区に大きな噴石が落下し、建物に被害も出ました。
そして、2006年6月、昭和火口が58年ぶりに噴火。2011年には年間に996回爆発するなど、活動は再び活発化しました。2015年8月15日には、急激な地殻変動が観測され、大規模な噴火の危険性が高まったとして、噴火警戒レベルが4に引き上げられ、火口3キロ圏の住民の避難も行われました。
そしておととし6月。爆発的噴火により、50センチから1メートルほどの大きな噴石が、火口からおよそ3キロ離れた集落近くまで飛散。監視カメラでは確認できず、判明が数日後だったため、監視体制のあり方など議論も呼びました。
そして、今月18日から山体膨張とみられる地殻変動が続いていましたが、24日の爆発的噴火で噴火警戒レベルが初めて5に引き上げられました。
注目の記事
「それならお前を殺す」中3の息子(15)は少年4人から暴行を受け命を奪われた 角材で殴られ、コンクリートの塊を投げつけられ「頭がでこぼこにへこんでた」【少年集団暴行事件・第1話/全4回】

【旧網走監獄】雑居房の床下から謎の文章13枚が見つかる 服役囚が隠した理由と文章の中身…半世紀以上の時を経て明らかに、記述から探るリアルミステリー
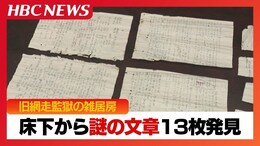
「手相が変わる」ってホント? 運勢をみるだけじゃない!手相が示す健康状態と生活のクセ「医学」と「占い」それぞれの解釈

「来熊」「来鹿」あなたは読める?意外と知らない九州・沖縄各県の「来訪・帰省」略語事情

【ヒグマ】焼却施設が限界 駆除数17倍で処理に追われる自治体が疲弊 1頭焼却に灯油100リットル 作業追いつかずに腐敗進み、埋めるケースも

「争奪戦になっている」1時間で完売のボンボンドロップシール 平成に流行ったシール交換が令和でもブーム










