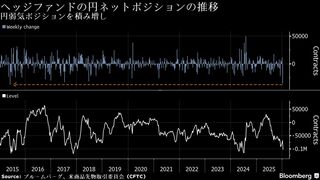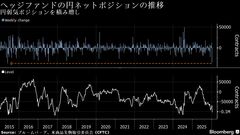(ブルームバーグ):ロンドンで気に入っているレストラン街の一つに、伝説的なラーメン職人の新しい店が間もなくオープンするというニュースを聞いて、私はニューヨークを懐かしく思い出した。
というのも、かつてマンハッタンのフードコート「ゴッサム・ウェスト・マーケット」で、汁なしのまぜ麺をほぼ毎日食べていた時期があったからだ。
濃厚なローストガーリックソースが絡む一杯を食べながら、私はノートパソコンで本の原稿を書き進めつつ、気難しい共著者との衝突に悩まされていた。
まぜ麺をはじめ、多彩なラーメンを提供していたのがアイバン・オーキン氏だ。ニューヨーク出身ながら東京で8年以上にわたり2店舗を成功させ、ラーメンの技とビジネスを極めた人物だ。
ゴッサム・ウェストの「スラープショップ(Slurp Shop)」はオーキン氏が米国に初めて出店したラーメン店で、私はそこで心身を満たし、にんにくの香りをまとうことで、共著者と本気で衝突せずに原稿を完成させることができたのかもしれない。
オーキン氏はスラープショップを始めた翌年の2014年、ローワーイーストサイドに「アイバンラーメン(Ivan Ramen)」をオープンさせた。今月19日、同じ名前の店がロンドンのファリンドンロードに開店する。
私が通うワインバー「クオリティーワインズ(Quality Wines)」のすぐそばだ。ロンドンとニューヨーク。私の愛すべき2つの都市の味が一つになる。
伝統主義者と革新派
23年まで日本を訪れたことがなかった私が、ラーメンに恋したのは日本ではなくニューヨークだったと言っても、驚くことではないだろう。それはラーメンという料理が持つ地理的な広がりと普遍的な魅力を物語っている。
ラーメンは、すしに次いで日本が世界に誇る代表的な料理となった。ピザやハンバーガー、フライドチキン、タコス、ドネルケバブと並ぶグローバルなメニューだ。
博多発祥のラーメン店、一風堂が海外で初出店したのは08年で、マンハッタンだった。「いらっしゃいませ!」と大声で客を迎えるあの演出を今でも鮮明に覚えている。
ピザと同じく、ラーメンも伝統主義者と革新派がせめぎ合う舞台だ。何が正統で何が許容されるかを巡り議論が絶えない一方、実験的な料理人たちがその境界を押し広げていく。
東京でオーキン氏は自家製の全粒粉麺を導入し、ラーメンは白い精製小麦粉で作るものだと主張する専門家たちを驚かせた。
今や全粒粉は、ラーメンにとって多様な表現の一つとなっている。オーキン氏によれば、欧米の客の中にはユニーク過ぎるとか、ユダヤ系ニューヨーク風過ぎて日本らしさが感じられないと不満を述べる人もいたというが、同氏はパイナップル入りラーメンを出す人気店もあると反論した。
ピザでも、トッピングのパイナップルについての論争は絶えない。ピザの生地では、厚みのあるシカゴか、薄くクリスピーなニューヨーク、あるいはナポリ風のふんわり生地かで、ほとんど取っ組み合いになるほどだ。
ある友人のモダン派ピザ職人は、ピザをイタリアのものに縛られない普遍的な料理にしたいと語っている。
もろ刃の剣
ラーメンとピザの語源をたどると、どちらもレシピの柔軟性を示唆している。イタリア語の「pizza」はギリシャ語の「pita」、トルコ語の「pide」など「平たいパン」を意味する語に由来する。
ラーメンは中国語の「拉麺」、つまり「引っ張って伸ばす麺」が語源とされ、韓国語の「ラーミョン」、ウイグル語の「ラグマン」など、アジア各地で響きが似ている。
私は個人的に、福建省発祥の「滷麵」が語源に近いと考えている。比較的汁気の少ない北方の拉麺よりも、煮込み麺である滷麵の方が現在のラーメンに近い。
日本で19世紀後半、ラーメンが屋台で広まり始めたころに、福建や広東出身の中国人移民が多くいたこともその流れを裏付けている。つまりラーメンとは、文化を超えて自在に変化する料理の象徴なのだ。今ではコペンハーゲン空港でもちゃんとしたラーメンが食べられる。
しかし、ラーメンを主力とする外食産業にとって、それはもろ刃の剣(つるぎ)でもある。日清食品を創業した台湾生まれの安藤百福(出生名:呉百福)氏が1971年、「カップヌードル」を生み出し、ラーメンをファストフード中のファストフードにしてしまった。
ラーメンは世界中の学生の常備食となり、瞬く間に市場を席巻。2024年にはインスタントヌードル市場の規模が600億ドル(約9兆2700億円)を超え、冷凍ピザ(約230億ドル)を大きく上回った。お湯を沸かす方が、オーブンでピザを温めながら解凍するより簡単なのだ。
こうした商品の普及によって、オーキン氏や一風堂のような職人や専門店は、外食する価値のある高級ラーメンを訴求しなければならなくなった。
だが、拡大にはリスクもある。中国では1990年代後半から日本発のラーメンチェーン「味千」が爆発的に店舗を増やしたが、2011年に成分の伝え方を巡り批判が起き、香港証券取引所で株式が一時売買停止となった。
その後、味千(中国)の株価は11年の水準から約90%下落している。過剰な効率化や独自性の追求が本物らしさを損なう危険を示す一例だ。
「モモフク」
一方、一風堂は看板商品の豚骨スープの評価を保ちつつ、100店舗を超える海外展開を進め、時代に合わせたメニューを導入している。豚骨を避けたい客向けに、きのこベースのスープを提供するなど柔軟に対応している。
オーキン氏は現在、自家製麺を作っていないが、ハワイの名門製麺会社「サンヌードル」と提携し、理想の歯ごたえを実現している。
オーキン氏の名声も顧客を引き寄せる要因だ。17年にはNetflixのドキュメンタリーシリーズ「シェフのテーブル」に登場し、米国人として日本でラーメン文化を極めた職人として知られる。
オーキン氏は今年、期間限定でロンドンに出店したが、私はニューヨーク時代と変わらぬ味を確かに感じた。オーキン氏が姿を見せれば、客たちはサインを求めたり、見とれたりする。
こうした名声ははかなく消えることもあるが、長く愛され続けることもある。カップヌードルを生み出した安藤氏はそのシンボルだ。同氏の業績に敬意を表し、米国の有名シェフ、デービッド・チャン氏は04年に自身初のレストランを「モモフク・ヌードルバー」と名付けた。
07年に96歳で亡くなった安藤氏が始めた日清食品ホールディングスの時価総額は、今や50億ドルを超えている。
(ハワード・チュアイオン氏は、ブルームバーグ・オピニオンのコラムニストで、文化とビジネスを担当しています。以前はブルームバーグ・オピニオンの国際エディターで、米誌タイムではニュースディレクターを務めていました。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:How Japanese Should That Bowl of Ramen Be?: Howard Chua-Eoan(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.