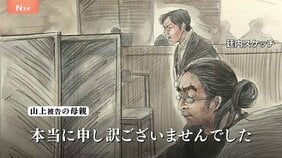このため親子で代々同じ人形を受け持つこともあったそうです。人形ごとの動きやしぐさは保存会の間で伝えられていきます。
(反省会で)「レプリカとご神体(本物)違いがあるから必ず確認して、」「4年たつと皆忘れちゃう」4年ぶりの緊張感の中でも和やかに準備が進みました。
保存会会長インタ「(中断で)祭りが途絶える心配はなかった・・・」
祭り当日、鈴宮諏訪神社に着いた9体の人形は境内に作られた「御船」に入り、舞いが始まります。
舞いは編木、太鼓、笛など楽器を持った人形が2体1組で踊ります。
途中でお囃子が変わり、手拍子も加わって動きが激しくなります。
「お狂い」と呼ばれるパートでは昔の民俗芸能の熱気が伝わります。
1体で舞う「御鹿島様(おかしまさま)」
木の小刀が投げられ観客は競って拾います。
最後は「御姫様」と「鬼様」の舞い、
物語が感じられる出し物で、天津司舞が日本最古の人形芝居と呼ばれる所以です。
およそ45分にわたって披露された4年ぶりの天津司舞。
神社に戻った人形は1年間の眠りにつき、これからも歴史を積み重ねます。
保存会会長インタ「以前の3倍くらい人が来てくれた、これからも・・」