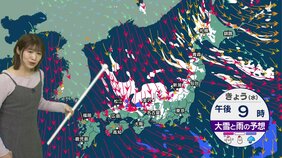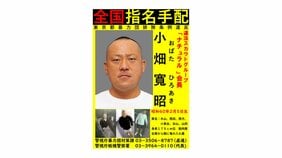3月11日、福島県浪江町の南津島地区に伝わる伝統芸能、田植踊りが披露されました。この田植踊りは、地区が原発事故で帰還困難区域となったことから、存続の危機に瀕しています。こうした中、地元出身の大学生が中心となって、住民から踊りを受け継ぐプロジェクトを立ち上げ、奮闘しています。震災から12年となった節目の日に、住民と学生の思いが実を結びました。
3月11日、仙台市の公共施設で、多くの人が見つめる中、浪江町で長い間受け継がれてきた太鼓と笛の音が響き渡りました。上演されたのは、福島県の重要無形民俗文化財、南津島の田植踊りです。

五穀豊穣や無病息災を祈る踊りで、始まりは200年以上前と言われています。かつては、毎年2月に地域の神社や寺に奉納し、家々を回って披露されてきました。原発事故で、踊りの担い手は各地に避難してバラバラになった上に、南津島地区は帰還困難区域となったため、いま、存続の危機に瀕しています。

この日、特別な思いで舞台に立った女性がいました。今野実永(こんの・みのぶ)さん。南津島の出身です。
今野さんは進学した東北学院大学で、田植踊りを学生が継承する「南津島民俗調査プロジェクト」を立ち上げ、これまで半年間にわたって、地域の人から踊りの手ほどきを受けてきました。

東北学院大・今野実永さん「私たちはあくまでも南津島の方々から(踊りを)お借りしている状態ですので、最終的には南津島の方に踊りを返せるように、しっかり継承しつつ、帰還困難区域が解除されたらぜひその地で学生みんなで踊っていきたいと考えています」
東北学院大・金子祥之准教授(プロジェクトを指導)「私たちはあくまでリレーだと思っているんですね。本来であれば津島の人たちだけでリレーを続けていければいいところを、よその人がかかわらないとバトンを継ぐ人がいなくなってしまったので、そこに参加させていただいているというつもりでいます」
2月26日には、初めて学生だけで踊りを披露し、複雑な動きや言い回しを再現しました。
南津島郷土芸術保存会・三瓶専次郞会長「若い学生さんたちが、覚えるのも早いけど、立派に披露してくれたなと。本当に思いがけない成果を出してくれたなと」

指導にあたってきた保存会の会長、三瓶専次郎さんも、手応えを感じています。