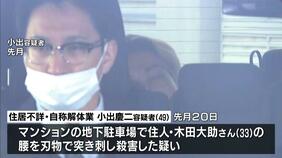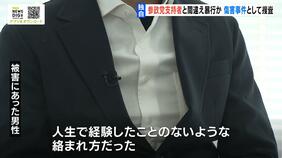不透明感残した会見 再生の道のりは
本多理事長は“個人的な感想”としたうえで「会社のなかの組織の習俗のようになっていて、正常化に向かって溶け出すまでには時間があった」とさらに表現した。また、不正融資の証拠が残っていたとされるノートパソコンが個人の独断で破壊されたという証言については、「破壊されたとされるパソコンの確認はとれていないが、内部調査でも第三者委と結論は同様だった」と話し、不透明感を残した。「破壊した」という証言については「組織の中にいる人間としては回答自体に強い疑念を持つというまでではなかった。それもあるのかなという感想だ」と述べた。
会見が開かれた5月30日現在では、無断で口座を開設された個人客には直接、謝罪はしておらず、今後、組合で直接謝罪したいと述べるにとどまった。また、主体的に不正に関わった役員については刑事、民事の両面で責任追及を図っていきたいと表明。一連の不祥事を受けて6月13日の通常総代会で本多洋八理事長以下、現在の役員9人のうち7人が責任を取って辞任し、上部団体の全国信用組合連合会と、さらに外部から人材を迎え、新たな役員体制で経営の抜本的な刷新を図るとした。また、東北財務局の業務改善命令を受けて、6月30日までに業務改善計画を提出することにしている。

「まだ全容解明にはいたっていない」とした第三者委の調査はこれで終了し、いわき信用組合は、今後さらに内部調査を進め全容解明していくとした。しかし、異様な隠ぺい行動を含め、調査に非協力的だったいわき信用組合の内部調査ですべてが明らかになるかは甚だ疑問が残る。
金融機関としてだけでなく企業ガバナンス(統治)のあるべき姿として大きな禍根を残した一連の不祥事。震災、原発事故を経て立ち直ろうとしている中小企業を中心とした被災地の経済に大きな影を残し、「地域の大事な金融機関だから存続してほしい」という地元の声に甘え、今後も胡坐をかくようでは「再生は難しい」と言わざるを得ない。