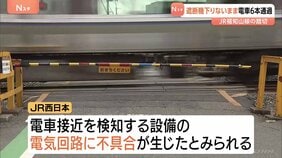いつ頃作られたエレベーターから、ドアに「複数のビーム」が?

――ちなみにエレベーターに一般的にこのような「センサー」が装備され始めたのはいつ頃なのでしょうか?
「前述のとおりの『片側から光が出て、もう片方が光を受信する』という仕組みのセンサー自体は、1970年代のエレベーターからすでに装備されていました。しかしこの時代のセンサーは、ドアに1つ、形も豆電球のようなものでした」
「現在のようにセンサーが細長く何個もついたのは、1990年代ごろからでしょうか。現在では、ほとんどすべてのエレベーターで標準装備となっていると思います」
なるほど。約30年前にはこの技術が導入されていたのですね。
「思いやりの心」否定はしません!が...
――そもそも、この「降りる前に【閉】を押す」という文化についてはどう思われますか?
「他の階で待っている人や、エレベーターに乗り合わせた人の待ち時間を少しでも短くしよう、という『思いやりの心』からくる行為ですよね。このような行為を見ると、『優しい人だな』と思うこともあると思います」

「また、この行為自体が『エレベーターの故障の原因となる』などの悪影響があるわけでもないので、積極的に否定するものではありませんが…」
「…とはいえ、『【閉】ボタンを押しながら降りる』ようにしても、早くドアが閉まることはないので、『慌てず、普通に降りる』のがいちばんかと思います。安全上のことを考えても」
結論!出るときは「慌てず普通に降りましょう」
という訳で結論としては、新しそうなエレベーターでは、出るときに【閉】ボタンを押しても早くドアは閉まることはない。。。
だからと言って、【閉】ボタンを押して出る人がいても「それ、意味ないんですけど!!」と目くじらを立てて否定するのではなく、「優しい人なんだな」と温かい目で見守ってあげる。
それが同僚でしたら、機会があったら教えてさしあげて「え、マジですか?!」とその場がちょっと盛り上がる、、、くらいで如何でしょうか。

日常の些細なひとコマですが、ちょっと覚えておくといい豆知識でした。
撮影場所:RSK山陽放送
モデル:たまたま夜、社内に残っていた杉澤眞優キャスターと、帰宅しようとしていた古米沙世リポーター