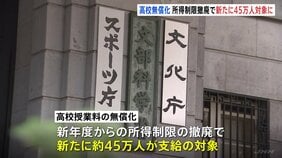シオカラトンボは益虫だった
(東洋産業 大野竜徳さん)
「トンボの一生は、水中と空中の二つの舞台に展開されます。卵からかえった幼虫ヤゴは、池や田んぼの底で数か月から一年を過ごし、見た目こそ地味ですが立派な肉食ハンターです。
小魚やオタマジャクシに忍び寄り、下あごをビュッと伸ばして一瞬で捕らえる姿は、水中のスナイパーさながら。やがて、成長すると水面へ上がり、羽化を迎えます。潜水艇のようだった体は、一気に戦闘機へと変貌するのです。
トンボはセミのように蛹を経ず、幼虫から成虫に直接変わる『不完全変態』の昆虫です。水中から空中へ、休むことなく一瞬で生活の舞台を切り替えるその転身は、トンボの大きな魅力の一つです」
「さて、シオカラトンボといえば鮮やかな青白い体色が印象的ですね。しかし、この青白さをまとうのはオスだけで、しかも羽化直後は黄色と黒の地味な姿をしています。
この時期は『ムギワラトンボ』と呼ばれ、稲穂や草むらに溶け込む迷彩柄です。時間が経つにつれて体表から白いワックスのような粉が吹き出し、光の乱反射で青白く見えるようになります。
これは、オスが大人になった証であり、いよいよ縄張り争いやメスへのアピールに参戦する装いです。
一方で、メスは『ムギワラトンボ』のまま成熟することが多く、雌雄を見分ける手がかりにもなります」
ーいままで、シオカラトンボといえば青白いものと思い込んでいました。
「この変化は人間でいえば、身だしなみを整えて社会に出る姿に似ています。青色の戦闘服をまとう頃には、オスは縄張りを主張し、ライバルと戦い、メスに求愛するようになります。
さらに、この粉は紫外線から体を守る効果もあり、真昼でも元気に飛び回るための頼れる装備なのです。
シオカラトンボは空を自由に飛びまわる捕食者で、蚊やユスリカ、小さなハエが大きな複眼に捉えられると、空中であっという間に捕獲します。彼らがいなければ、夏の水辺は小さな虫であふれ返っていたかもしれません。まさに天然の害虫駆除屋さんです」
ー私たちにとっては、益虫だったのですね。
「しかし、彼らもまた多くの生き物に狙われます。ヤゴは魚や大型水生昆虫の餌に、成虫はツバメやカワセミ、カエル、さらにはムシヒキアブや他のトンボに捕らえられることもあります。シオカラトンボは食べる側でありながら、食べられる側でもあり、水辺の食物網を支える重要な存在なのです」