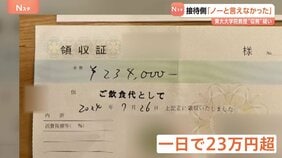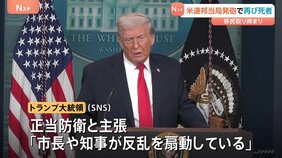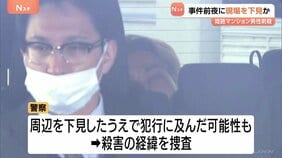「苦味」は「舌で感じるもの」という、これまでの常識を覆す研究成果が発表されました。
「皮膚」にも角化細胞内に「舌と同一の苦味受容体」が存在し、「苦味」を感知し、その元となる有害物質を体外に排出するなどの重要な働きがあることを、世界で初めて突き止めたということです。
研究は、岡山理科大学生命科学部のバイオサイエンスコースとコスメ食品コースの共同研究グループが、京都大学大学院薬学研究科と東京大学大学院薬学系研究科、および医学系研究科と共同で進めたもので、8月27日にその成果が米国実験生物学会連合が発行する科学ジャーナル「FASEB BioAdvances」電子版で公開されました。
「苦味」は有害物質であることの警告になり、舌の場合、味細胞にある「苦味受容体」が感知すると、拒絶することで口からの侵入を防ぐ役割を果たしています。
今回の研究では、舌と同様に、「皮膚の角化細胞内の小胞体にある苦味受容体」が、侵入した有害物質を感知(結合)することで活性化され、排出ポンプ作動のためのスイッチをオンにすることで有害物質を細胞外に排出する、一連の生体防御的役割を始めて明らかにしました。
ただ、有害物質の中には「苦味受容体が感知できない物質」もあり、そうしたケースでは、その物質は細胞内で蓄積し、皮膚障害や炎症などを引き起こす恐れがあります。
研究ではそのような場合、人為的に「皮膚の苦味受容体を活性化」し「排出機能をオン」にすれば、細胞外に有害物質を排出させられるとして、今後、無害で受容体を活性化させる薬剤の開発により、皮膚の保護剤や炎症治療につながる可能性が期待できるとしています。