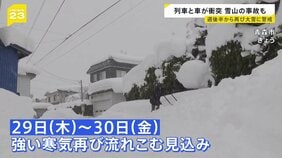郷原さん「災害が多い時代にも良いのではないかと、天竺様を主に構造を形成する建物を建てています」
『天竺様』とは伝統的な建築様式の一つ。現在用いられている建物は、国宝である奈良の「東大寺南大門」と兵庫の「浄土寺浄土堂」の2ヶ所だけです。
特徴は複雑な木材の組み方。「長延寺」の天井付近にある「挿肘木(さしひじき)」と呼ばれる柱の部分で技術が光ります。

郷原さん「柱の左側の木と右側の木は1本で柱を貫通しています。肘木(ひじき)も柱の中でかみ合っているやり方。木と木が交差し、綺麗にかみ合っています」
特別に近くで見せてもらうと、柱を貫通する複数の木が柱内部で互いにかみ合う複雑な構造です。
郷原さん「柱を持ち上げて(横から木を)入れて落とす感じ。同時に3本やります」

釘や接着剤を使わずに、柱の安定感とデザイン性を両立させています。
また、屋根を支える「垂木(たるき)」の部分にも工夫が。通常、垂木は平行に並べますが、ここでは「扇状」に。そうすることで、頑丈さが増すといいます。

様々な技術が組み込まれた長延寺、しかし実際に組み上げていくまでには2年もの時間を要しました。