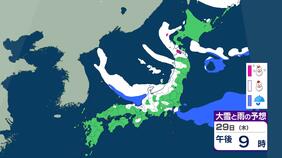「内密出産」などで生まれた子どもたちが、親や生まれ育った環境などを知る「出自を知る権利」について議論を重ねてきた検討会が、21日、熊本市の大西市長に報告書を提出しました。
報告では「父母に関する情報の開示は18歳以上が適切」などと位置付けています。
『出自に関する情報』五つのポイント
報告書では、父母の身元に関する情報や妊娠のいきさつなどの『出自に関する情報』について、「どのように収集し」、「どこで、どのように保存するか」、また、子ども本人に開示するのは「どのような年齢が適切か」など五つの点について、一定の指針を示しました。
<検討のポイント>
・出自に関する情報の “分類”
・出自に関する情報の “収集”
・出自に関する情報の “保存”
・出自に関する情報の “開示”
・子どもが出自に関する情報を知るプロセス(真実告知)
このうち、父母に関する情報などについて開示請求が可能になる年齢は「18歳が適切」と明記したうえで、子どもの精神的な安定度と、サポート体制の両方が整っていれば15歳以上でも可能としました。
その理由について報告書では、
▼18歳が成人年齢に達する時期であること
▼子や母親の状況の変化を考慮したこと を挙げています。
また、父母の身元に関する情報や子どもへの思いなど、出自に関する情報は父母などからの聞き取りによって確認し、その際に「確認書類の提出は求めない」としました。
「こうのとりのゆりかご」「内密出産」の課題

熊本市では、市内にある慈恵病院が親が育てられない赤ちゃんを匿名で託す「こうのとりのゆりかご」(いわゆる「赤ちゃんポスト」)や母親が病院にだけ身元を明かして出産する「内密出産」を独自に運用しています。
こうした運用により、誰にも相談できずに自宅などで隠れて出産する危険から母親と子どもの命を守ることにつながりました。
一方で養親などに育てられた子どもがどのように生まれたのかを知る「出自を知る権利」や、その知らせ方などが課題になっていました。
そのため慈恵病院は熊本市とともに検討会を設置。弁護士などの有識者のほか、「ゆりかご」に預けられた子の養親など18人が、海外での先行事例などを基に2023年から12回にわたる議論を続けていました。
報告書 その他のポイントは
これまで「ゆりかご」などに携わる人からは、匿名性を貫くことを認めない場合、「ゆりかごの利用などをためらう女性が現れ、母子の生命に危険が及ぶ」との指摘もありました。今回の報告書は、こうした声が考慮されたものとみられます。
最後にこうした出自情報の現時点での管理・保存先は、受け入れた医療機関(慈恵病院)と児童相談所を指定し、情報の性質によっては開示にあたり、父母の同意が必要と定めました。
検討会は今回の報告書を基に、現在は慈恵病院が独自に実施している内密出産や「出自を知る権利」について、熊本市が中心となり国に法制化を求めることなども提言しました。