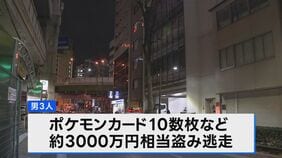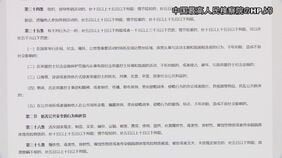ペシャワール会の中村哲医師が亡くなって5年。九州大学(福岡市)の後輩が、中村さんの遺志を語り継ぐ取り組みを進めている。1月17日には、フォトジャーナリストの安田菜津紀さんと学生たちが語り合うイベントが開催された。RKB毎日放送の神戸金史解説委員長が、1月28日放送のRKBラジオ『田畑竜介GrooooowUp』でそのもようを伝えた。
後輩が継ぐ中村哲さんの遺志
中村哲さんが卒業した九州大学には「哲縁会」という学生団体があります。卒業生である中村哲さんの遺志を学び、読書会などで広く発信していく活動を続けています。

【中村哲さん】
ペシャワール会現地代表。1946年、福岡県生まれ。九州大学医学部卒業。国内の病院勤務を経て、84年パキスタン・ペシャワールのミッション病院ハンセン病棟に赴任、パキスタン人やアフガン難民のハンセン病治療を始める。2000年から、干ばつが厳しくなったアフガニスタンで飲料水・灌漑用の井戸掘削を始め、2003年からは農村復興のため大がかりな水利事業に携わる。2019年12月4日、銃撃され死亡した。
哲縁会が1月17日、フォトジャーナリストの安田菜津紀さんを招いて、「良心を繋(つな)ぐ仕事」というテーマで意見交換しました。一般公開されたイベントだったので、会場の九大西新プラザには100人以上が詰めかけました。
九州大学共創学部3年の阪井翔大さん(22歳)が、安田さんに語りかけました。

阪井:安田さんは「現場を伝える仕事」をされています。それに対して、中村哲さんは「現場で支援する仕事」、現場で支援する側の人物です。どちらの立場も重要であることは前提ですが、それらの世界の問題、社会問題に対する向き合い方や違いについて、掘り下げていきたいと思っています。会としては、中村哲さんの本や会報、言葉から引用して、安田さんがそれをどのように解釈されて、現場をどういう風に伝えていらっしゃるのかうかがい、最後には「良心をつなぐ仕事とは何か」について考えていきたいと思います。
中村さんが安田菜津紀さんに与えた影響
安田さんは講演で、シリアで空爆を受け片足を失ってしまった8歳の女の子の言葉や、イスラエルの高校教師が、ガザで犠牲になった子供たちの写真とともに「この狂気を止めるんだ」とSNSに投稿したら、学校から解雇され逮捕されたことを紹介しました。現場の見聞、戦争の実態を説明しました。

【安田菜津紀さん】
1987年、神奈川県生まれ。フォトジャーナリスト。認定NPO法人DialogueforPeople副代表。東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で、難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は岩手県陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)ほか。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

学生との対話が始まりました。医学部4年の木原秀将さん(23歳)は、「中村哲さんのことをもっと知りたい」と思って九大医学部に入学したのだそうです。木原さんは中村さんのこんな言葉を引用して質問しました。
中村哲さんの言葉:「もはや議論や声明だけで済ますには、事は余りに重大です。平和の志向は、人為の小世界に欺かれず、いのちを尊び、実際行動で力を持つべきです」(ペシャワール会報76号、2003年)
木原:安田さんは、写真というより多くの人に伝わる方法を用いて、行動をされていたと思うんですけども、中村哲先生の意志のどのようなことに共感されているのか、そのことがどう今の実際行動につながっているのか、を聞かせていただきたいと思います。
安田:私たちはやはりどうしても、中村さんたちの活動と比べると、現地取材も短期ですし、ともすると相手のカルチャーや距離感のあり方を無視して、土足で踏み込んでしまうおそれがすごくあると思うんです。でもそうではなくて、なるべく許される限りで、例えば一緒に食卓を囲ませてもらったり、言葉を覚えたり。取材って、すごく時間をいただき、言葉をいただいているものなんだということを忘れないようにしたいと思えたのは、中村さんのそういう姿勢に触れたのもすごく大きかったと思います。

安田:私たちが何枚写真を撮っても、被災地の瓦礫がどけられるわけではない。そういうことをぐるぐる考えていた時、ペシャワール会とは違う別のNGOの方だったんですけれども、「これは役割分担なんですよ」という言葉を、現地で支援する方からいただいたことがあったんですね。「確かに、自分たちは地元に残って必要な人に必要なものを届けながら、寄り添って活動することができるかもしれないけれど、でも現場がいっぱいいっぱいになるほど、『ここで何が起きているのか』を世界に発信することに力が割けなくなっていく。あなたは少なくとも、”通う”ことはできるんだし、ここで何が起きているのか発信することができるよね。役割分担だよね」と言われた時に、もちろんそれで葛藤がなくなるわけではないんですけど、自分の取るべき行動みたいなものの道筋が見えたような気はしたんですよね。
こんなやり取りが行われていました。「役割分担」という言葉は、印象に残りました。