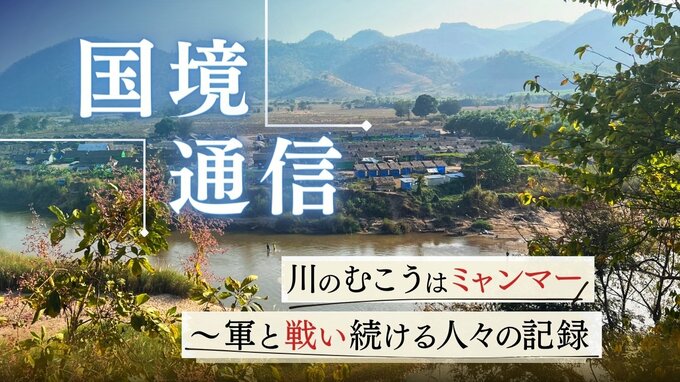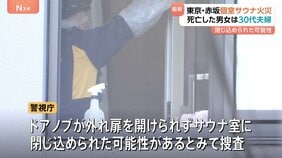2024年3月にこれまで勤めていた放送局を退職した私は、タイ北西部のミャンマー国境地帯に拠点を置き、軍政を倒して民主的なミャンマーの実現をめざす民衆とともに、農業による支援活動をスタートさせた。
当初柱にすえていたベビーコーンが思ったほど収穫できないなど紆余曲折あったが、私たちは、ようやく「オクラ」という、ビジネスにつながる光を見出した。
◆指先は爪の中まで土で真っ黒 祈るような気持ちで種まき

アインの農園でオクラの栽培が始まった。種まきには私も参加した。整備された畝(うね)に深さ2~3センチの穴を作り、そこに3粒ほどの種を落として土をかぶせていく。
「ようやく本格的に野菜の栽培をスタートすることができる。どうしても失敗したくない、、、」
私は少しでも発芽がうまくいくようにと、穴を掘ったらその土を指で柔らかくほぐし、種の上にそっとかぶせるように作業していた。
しかし、そんな面倒なことをしているのは私だけで、ほかの人たちは木の枝で土の表面をガリっと削ったところに種を落とし、土をかぶせたかどうかもわからない状況で、さっさと作業を進めていく。おのずと作業スピードに差が出て、種まきの列の中で私だけが取り残されていくという状況が生まれた。見かねたアインが近寄ってきて、笑いながら声をかける。
「ブラザー、そんなに丁寧に作業しなくていいんだ。見ろ、手がこんなに汚れてしまって」
たしかに、私の指先は爪の中まで土が入って真っ黒だった。しかし、私は頑固に土をほぐしてかける、という作業を続けた。この程度のひと手間で、発芽の可能性が少しでも高まるなら安いものだ。農業の素人で、土をほぐすことで本当に発芽の可能性が高まるのかもわからないくせに、私はどうしてもこのひと手間を惜しみたくなかった。ようやく事業に光が見えたのが、今回のオクラの栽培なのだ。祈るような気持ちで種の上に土をかぶせ続けた。
とはいえ、こんなやり方をしているのは私だけで、圧倒的に作業スピードが遅いので、私がまいた種は全体のごく一部に過ぎない。要するに、ただの自己満足だった。私以外の人々の効率的な作業によって、今回予定していた5ライの農地への種まきは2時間ほどで修了した。
タイでは土地などの広い面積に使われる「ライ」という単位がある。1ライは、40メートル×40メートル=1600平方メートルなので、今回オクラの栽培にあてたのは5ライ=8000平方メートル。アインの農園の半分以上を充てた形で、私はオクラに対するアインたちの期待も、ひしひしと感じていた。
◆鮮度保ったまま7時間 課せられた収穫と輸送のミッション

この日は、オクラを買い取ってくれる協力企業の担当者も現場に立ち会っていて、種まきを見届けたあと、今後予想される害虫や病気、その際に使用すべき農薬の確認を一緒に行った。
収穫できるまでに要する期間は約70日。そのあとは約2か月の間、毎日収穫することができる。逆に言うと、毎日オクラの収穫作業が必須になるということで、そのための人手の確保という課題もあったが、アインは「私の周りには働きたがっている避難民が大勢いる。心配いらない。」と頼もしい。

私たちの計画では、収穫されたオクラは現地にある冷蔵庫に一旦保管し、鮮度を保った状態で企業のもとに届けるために少なくとも3日に一度、まとめてバンコク近郊まで輸送することになっていた。輸送にもコストがかかるため、それも含めてオクラの単価は決定される。
どうやって輸送コストを抑えるのか、企業側に相談していたが、はっきりとした方針は示されていなかった。担当者が自ら車を運転して運ぶ、といった案もあったが、バンコクからは車で約7時間かかり、3日に一度のペースで往復を続けるのは現実的ではないように思った。この問題も含め、実はこの時点でオクラの買取価格について企業側から具体的な数字は示されていなかった。
合意していたのは5ライという規模で栽培し、収穫されたオクラは基本的に全量を企業が買い取ること、それだけだった。アインが調べてくれた地元市場でのオクラの買取価格は担当者に伝えていたので、それよりは高い価格で買い取ってくれることが、そもそもこの事業の前提であったし、それは企業側も当然認識したうえで、ここまで作業してきたはずだ。