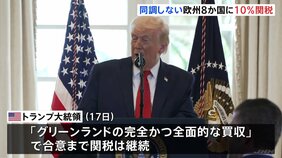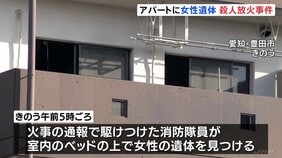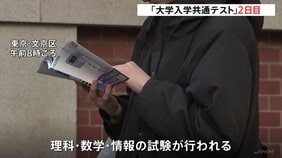メディアに「世論の監督」課す
この突発事態対応法は、起こり得る危機への対応を、法律面でさらに強化しようというものなのだろう。ただし、ここからがポイントだが、改正前の条文、改正後の条文を並べて読み比べてみると、気になる点がある。
それは「メディアの役割」だ。中国報道に携わってきた者として、見過ごせない。改正法の第8条にこんな条文がある。
“「緊急事態において、国家は健全な報道・取材システムを構築する。関係する政府や関係各部門は、報道機関を適切に指導する。合わせて報道機関が行う取材活動、並びに、世論を監督する行為を支援する」”
「健全な報道・取材システムの構築」、「報道機関への指導」「世論を監督する」…。中国のメディアは「中国共産党の宣伝機関」の役割を持つ。改正前の緊急事態対応法には、メディアに対する管理について、これほど明確な文言はなかったが、新たに盛り込まれた。
「世論を監督する」とは、インターネット上で流れる情報や意見、とりわけデマ、不正確な情報があふれないように、正しい報道をしろ、ということだろう。ただ、ここでいう「正しい報道」とは、当局の発表に基づく報道、当局が認めた報道のことであり、日本など海外のメディアの「正しい報道」とは意味が異なる。
中国政府が警戒する「タキトゥスの罠」
中国メディアで働く人たちの組織が、今回の突発事態対応法の改正に伴って、各メディアに対して、こんな通達を出している。
“「ネット上の社会では、情報の透明性に対する国民の要求が高まり、虚偽の情報への許容度が広がっている。緊急事態の発生後、情報が即座に公表されず、取材や報道が追いつかずなければ、ありとあらゆる虚偽情報、デマやウワサが広がる。『タキトゥスの罠』、といった状態に陥ることさえ、あり得る」”
「タキトゥスの罠」とは、古代ローマの歴史学者・タキトゥスが述べたとされる言葉だ。政府に対する信頼が大きく失われてしまえば、真実であっても、政府の言うことが民衆から全く信用されなくなってしまう――そのことを意味する。
“「今日、国内外の環境は大きく変化し、一部で過熱した声が、容易に燃え上がるケースが、たびたび起きている。ネット上の世論は複雑になっている。緊急事態が発生した場合、メディア人としてどのように、よい仕事をするか――。新たな課題が突きつけられている」”