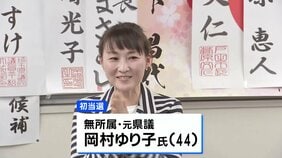◆すべてはナンバー1が支配する
「首相が口を開かなくなる」「口を開く必要はない」――。この観点から考えよう。二つ、意義付けられる。一つ目は、中国という国がどのような方向へ進んでいくか、それは政府や国会ではなく、共産党だけが、すべてを進めていくと宣言したといえる。
中国の政治システムは「共産党が国家を指導していく」わけだが、個々の政策は、政府が立案し、議会が承認してきた。これからは党が進め、政府はわずかに補完する役割に回る分岐点になったということだ。
二つ目。「首相は中国の序列2位」と表現されてきた。そのナンバー2は「しゃべらなくてよい」ということになる。さきほど紹介した全人代初日の政府活動報告。1年前に就任した李強首相にとって、今回が初めての活動報告の場だった。いわば晴れ舞台。それが過去30年間でもっとも短い時間だった。これまでも指摘してきたが、習近平体制にあって「ナンバー2以下は存在しない」「すべてはナンバー1が支配する」――。そういうことだろう。
ただし、経済に限っても、不動産不況が長びく。消費も低迷し、中国経済は難問が山積している。今年の経済成長目標を「5%前後」に設定した。昨年の成長率は5.2%。今年の5%という目標達成は容易ではない。
外国メディアは、そんな疑問を首相に直接、尋ねたいのだ。李強首相に、自分の口から過去1年間の経済を総括してほしい。中国当局は公式には認めないが、すでにデフレ状態にある。国際的な投資家は「中国離れ」を加速させ、それを日本へシフトさせている。株が日経平均で初の4万円台というのも、中国要素が小さくない。
もちろん、彼らも危機感を持つ。中国の国営メディアはいま、さかんに「経済について心配するな」と国民に訴えている。「経済は全体として回復傾向にある。中国は世界経済の重要なエンジンであり続ける」と宣伝している。海外資本の中国への投資にも躍起だ。
しかし、そんな閉鎖的な、いまの中国のスタイルに、海外資本は懐疑的でもある。行政の最高責任者である首相が、だれもが懸念する経済について説明しない。「存在していたものがなくなる」「首相会見という、開かれていた窓が閉じられる」。そうなるとさらに懸念が広がる。さらに不安の声が出る。このような国に、積極的に投資できるだろうか。
当然、中国の指導部も、外からの目がわかっている。それでもやる――。今年の全人代をながめると、いかにも今の習近平政権を象徴しているように思えてならない。
◎飯田和郎(いいだ・かずお)

1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。